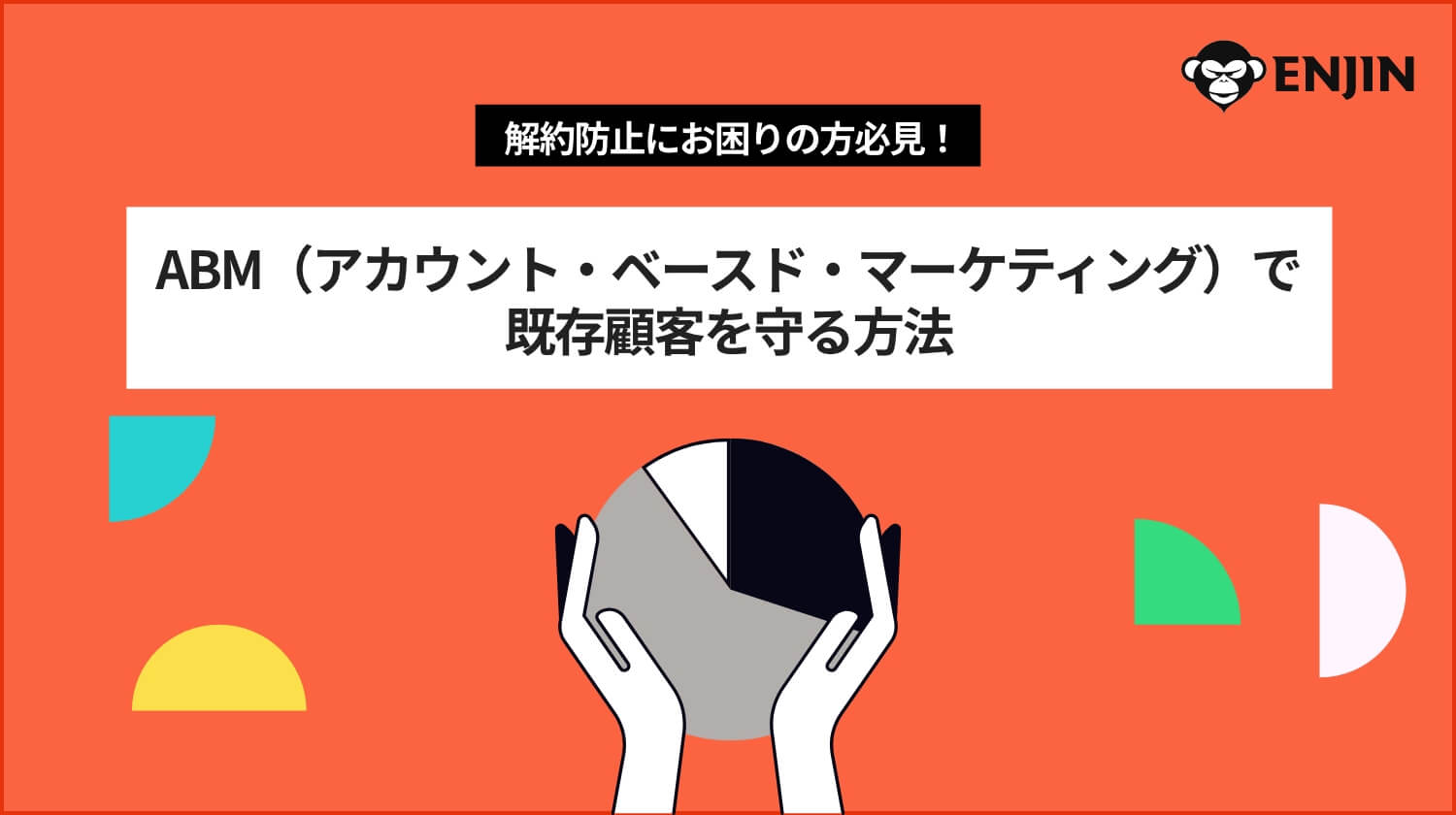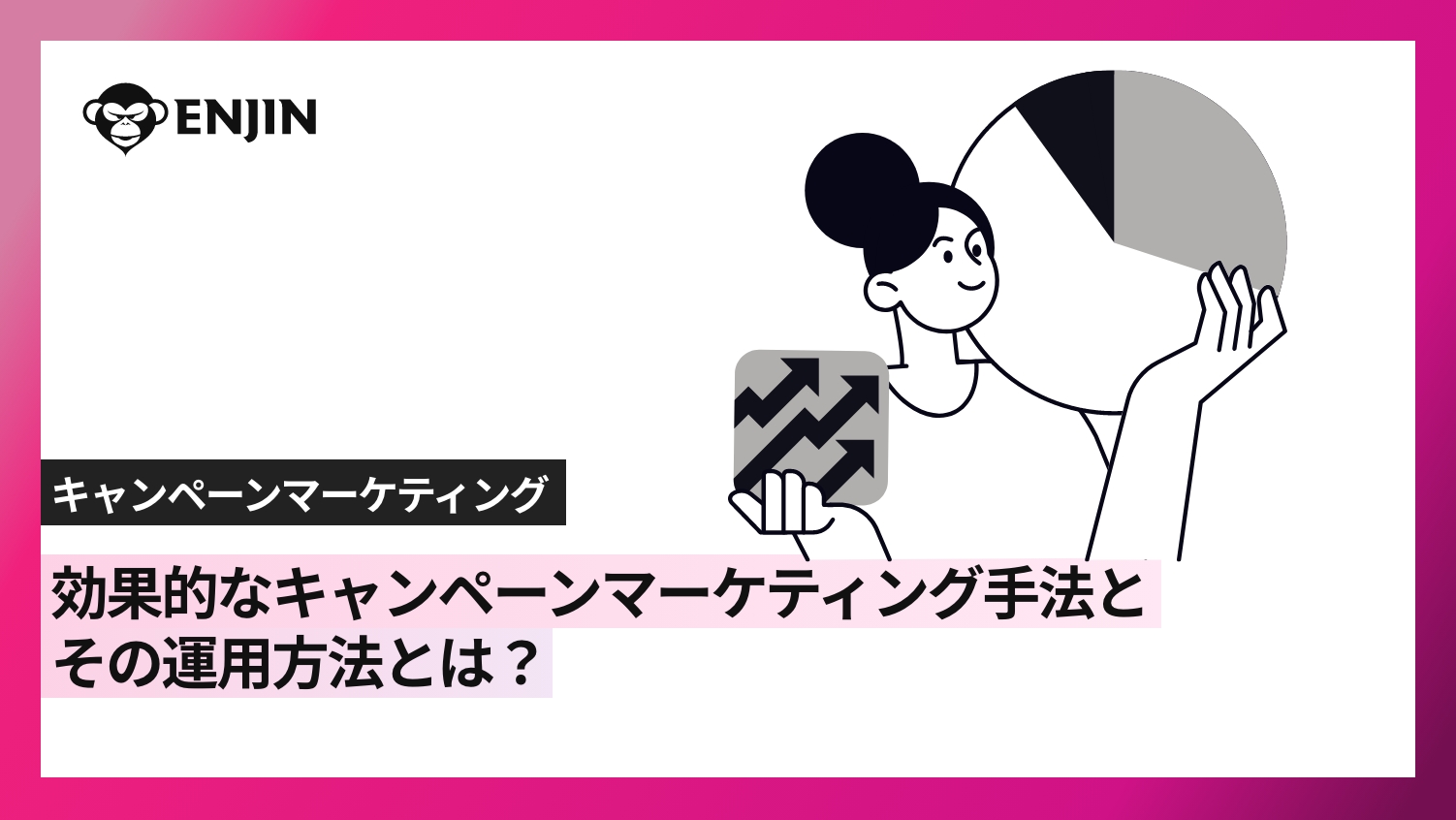BtoBマーケティングの戦略立案のプロセス!多様な施策やKPI設計についても解説
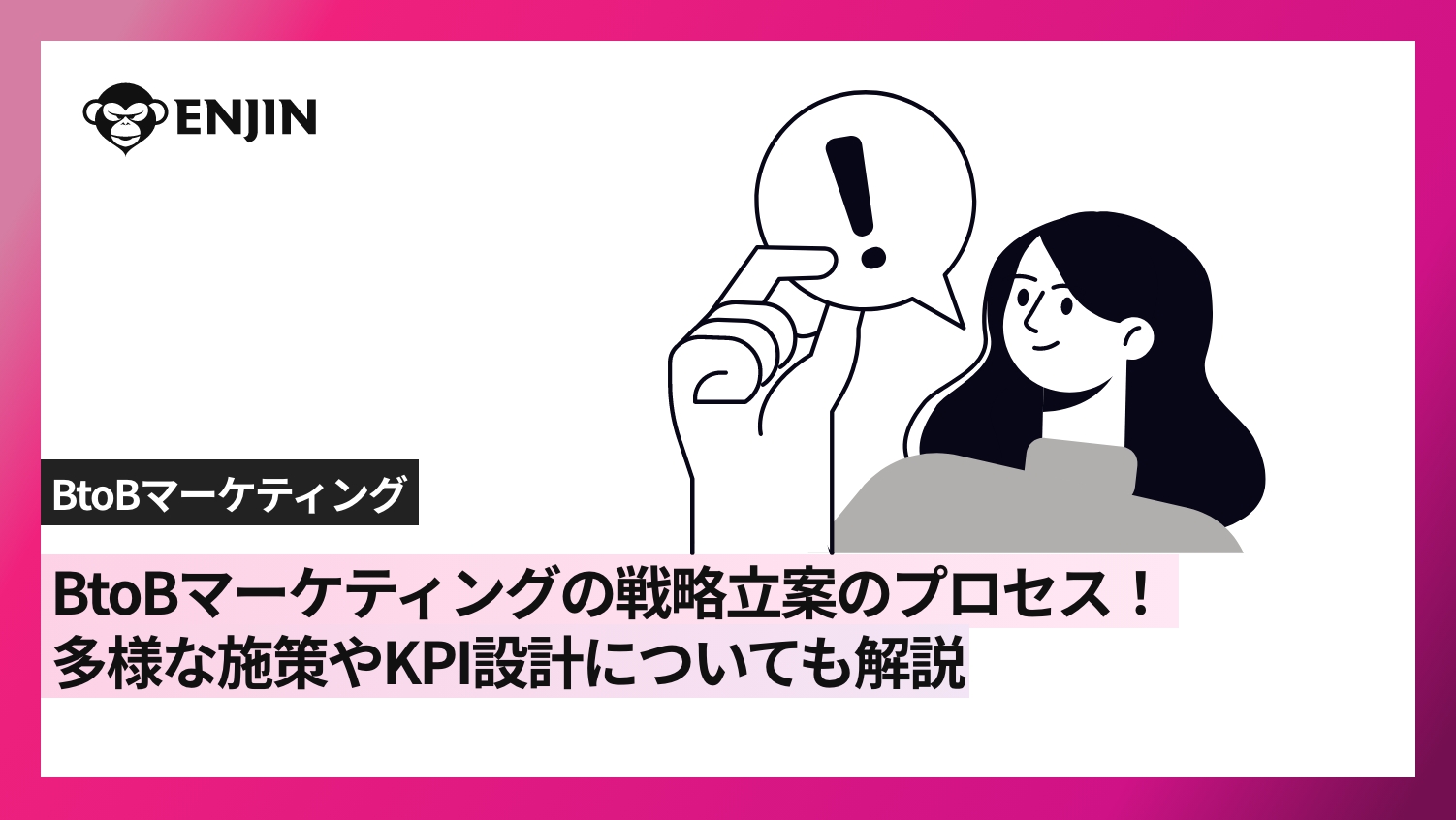
BtoBマーケティングに携わる方の中には「とにかく目の前のタスクを回すので精一杯で、戦略なんてどこから考え始めればいいのかわからない...」と感じている方もおられるかもしれません。
とくにBtoB領域では、商談化までの道のりが長く、ステークホルダーも多いため、思いつきで施策を走らせても、なかなか成果に直結しません。だからこそ、最初にしっかり戦略の“地図”を描いておくことが、成功への第一歩になるんです。
この記事では、そんなBtoBマーケティングの戦略立案について、考え方の基本から主要な施策、そしてKPIの設計まで、解説していきます。
ちょっと長いですが、お付き合いいただけると嬉しいです。
BtoBマーケティング戦略とは?BtoCとの違いから考える
そもそもBtoBマーケティング戦略って?──
ひとことで言うなら、「企業向け取引に特化したマーケティング活動の設計図」のようなものです。
よく比べられるBtoCと並べると、こんな違いがあります。
BtoB
| 購買単価 | 高額(数十万円〜数億円) |
|---|---|
| 関与者 | 多い(複数部署・役職者・稟議あり) |
| 検討期間 | 長い(数ヶ月〜1年以上) |
| 意思決定基準 | 論理的・合理的(費用対効果・品質・納期など) |
BtoC
| 購買単価 | 低額(数百円〜数十万円) |
|---|---|
| 関与者 | 少ない(基本は個人) |
| 検討期間 | 短い(即決〜数日) |
| 意思決定基準 | 感情的・直感的(好み・流行など) |
このように、BtoBでは「高単価」「複数関係者」「長期検討」「論理的な意思決定」が基本です。
つまり、「とりあえず話題になればOK!」というBtoC的なアプローチでは太刀打ちできないわけです。
だからこそBtoBでは、顧客企業様の課題と真剣に向き合い、信頼関係を丁寧に育てる“地に足のついた戦略”が求められます。
「BtoBとBtoCでは、そもそもスタート地点が違う」──そんな意識を持つことが、とても大切です。
なぜBtoBマーケティング戦略が重要なのか?
戦略がないまま、思いつきでマーケティング施策を進めてしまうと、どうしても「今できること」や「目先の数字」にとらわれがちになりますよね。
その結果として──
- 「誰に」「何を」届けたいのかがあやふやなまま進行
- コンテンツや広告のメッセージがバラバラで一貫性ゼロ
- 頑張っても成果につながらず、リソースだけムダに消耗
…なんて状態に陥りやすくなります。
でも、あらかじめマーケティング全体の“戦略”を設計しておくと、「いま、なぜこの施策をやるのか?」がちゃんと説明できるようになるんです。
たとえば──
-
限られた予算や人手の中でも、的確なリソースや予算配分がしやすくなる
-
営業チームとの連携がスムーズに進むようになる
-
中長期で成果に近づくストーリーが描ける
といったように、いろんなポジティブな連鎖が生まれてきます。
BtoBマーケティングでは、ステークホルダーが多く、施策の種類も多いからこそ、このように全体の方向性を整える“戦略”がとても大きな意味を持ちます。
【関連記事】BtoBマーケティングとは?効果的な戦略立案の方法と主要施策を紹介
BtoBマーケティング戦略立案の基本プロセス
BtoBマーケティングの戦略を立てるうえで大事なのは、「とりあえず思いついた施策をやってみる」のではなく、順序立てて考えていくことです。ここをちゃんと押さえるだけで、戦略の解像度はグッと上がります。
この記事では、BtoBマーケティングの戦略立案における基本的な流れを次の3ステップを基本プロセスとしてご紹介します。
①市場・顧客・自社・競合の分析
まずは、いきなり施策に飛びつく前に、“今どんな状況にいるのか”をしっかり把握するところからスタートします。
おすすめは、以下の4つの軸での現状分析です。
-
市場分析:業界の成長性、トレンド、外部要因の変化は?
-
顧客分析:ターゲット企業が抱えている課題やニーズって何?
-
自社分析:自社の強み・弱み、勝てそうな土俵はどこ?
-
競合分析:他社はどんなポジションを取っていて、何を仕掛けている?
この4方向からの“多角的な視点”を持つことで、「誰に、何を、どう届けるべきか?」のヒントが見えてきます。
さらに、こんなフレームワークを使うと、思考の抜け漏れを防ぎながら整理ができます。
(フレームワークはいっぱいありますが、全部利用しなければならない訳ではありません)
- 4C分析(Customer / Competitor / Company / Channel)
- SWOT分析(Strength / Weakness / Opportunity / Threat)
- PEST分析(Politics / Economy / Society / Technology)
ただし、たくさんやることがあるからという理由で分析を「ざっくり」や「なんとなく」といった表面的な進め方でやろうとすると、どこか他社と同じような戦略になってしまうといったリスクが生じます。分析は“焦らず丁寧に”進めましょう。
②ターゲティングとペルソナ設計
次のステップは、「どの企業の、どんな人にアプローチするか?」というターゲティングです。
BtoBでは、単に「この業界、この規模の会社」と決めるだけでは足りません。
その中で誰が意思決定に関わるのか?──
ここを深堀りしていくのがペルソナ設計です。
たとえばIT製品であれば:
- 情報システム部の部長(全体方針を握る人)
- 現場の担当者(実際に運用する人)
- 管理部門の決裁者(予算を握る人)
など、ステークホルダーが意外と多く、それぞれ立場や視点も違います。
大事なのは、それぞれの立場や悩みを想像して、“その人の目線で”情報設計すること。
そのためには、想像力を働かせて「どんな悩みを抱えていそうか」「何を気にするか」に寄り添う必要があります。
ターゲットが曖昧だったり、「業界は広めに」みたいなふわっとした設定だと、メッセージがぼやけてしまい、訴求も浅くなり、せっかくかけたリソースがムダになります。
ここは妥協せず、明確なターゲット像を設定し、成果につながるマーケティング活動を実現しましょう。
③カスタマージャーニーの設計
「誰に、何を届けるか」がクリアになったら、次は「どんな流れで届けていくか?」──
そう、カスタマージャーニーの出番です。
カスタマージャーニーとは、見込み顧客が「あなたの会社を知る(認知)」し、興味を持ち、比較・検討を経て、「導入を決める(購買)」までにたどるまでの一連のプロセスのことです。
それぞれのフェーズで、最適な情報や接点を用意しておくがマーケティング成功のカギになります。
たとえば:
-
認知フェーズ:広告、SNS、展示会などで知ってもらう
-
検討フェーズ:ホワイトペーパーや導入事例、ウェビナーで信頼を深める
-
比較フェーズ:個別相談やデモ、具体的な導入支援資料で背中を押す
こうした流れを“見込顧客の気持ち”に寄り添って設計することで、自然な形で商談や受注にスムーズにつながっていきます。
なお、このジャーニーの流れがバラバラだったり、途中で情報が途切れてしまうと、せっかく興味を持ってもらえていた場合にも薄れてしまうことがあるので注意が必要です。
カスタマージャーニーの設計は、とても重要な“つながり”の設計です。丁寧に、しっかり描いていきましょう。
BtoBマーケティング施策の全体像──TOFU・MOFU・BOFUでとらえる戦略構造
BtoBマーケティングでは、見込み顧客との関係づくりを一気に進めるのは難しく、
「知ってもらう → 興味を持ってもらう → 商談につなげる」という段階的なアプローチが必要になります。
この流れを整理するのによく使われるのが、「TOFU(認知)」「MOFU(関係構築)」「BOFU(商談化)」の3つのファネルです。
ここでは、それぞれのフェーズの役割や、代表的な施策について整理していきます。
TOFU(Top of Funnel)|認知・リード獲得フェーズ
| 目的 | 見込顧客と“はじめまして”の接点を構築し、認知してもらう |
|---|---|
| 提供価値の方向性 |
|
まずはターゲットと出会う場所を設けることが最優先です。とはいえ、ただ母数を増やせばいいわけではありません。
大切なのは“営業につながる確度の高い場を選定する”こと、です。
最初の接点を“質”で設計することが、後の成果に大きく影響してきます。
MOFU(Middle of Funnel)|関係構築・興味喚起フェーズ
| 目的 | 「この会社、ちょっと気になるかも」と思ってもらう |
|---|---|
| 提供価値の方向性 |
|
ここは、TOFUでつながったリードとの信頼関係をじっくり築いていくフェーズです。
BtoBの購買プロセスは長く、関係性づくりがとても重要となります。
相手が「情報を受け取ってもいい」と思ってくれているうちに、しっかりと価値を届けることができるかが分岐点となります。
継続接点の中で、“この会社わかってるな”と思ってもらえるような関係づくりを目指しましょう。
BOFU(Bottom of Funnel)|選別・商談化フェーズ
| 目的 | 興味を確信に変え、営業につなげる |
|---|---|
| 提供価値の方向性 |
|
MOFUで関係ができたリードの中から、「今声をかけるべき人」を見極めてアプローチしていくのがこのフェーズです。
ここでは、“今すぐ客”を見逃さず、自然な形で営業にバトンを渡すための仕組みが必要です。
もちろん、そのためにはマーケティングと営業が連携しておくことも忘れてはいけません。
実行フェーズに落とし込む:デマンドジェネレーション施策の実践ポイント
3つのファネルをつないだ全体像が描けたら、次は「実際に何をるか?」という実行フェーズに移ります。
ここで出てくるのが、リードジェネレーション(獲得)→ ナーチャリング(育成)→ クオリフィケーション(選別)という3つのアクションです。この流れは「デマンドジェネレーション」と呼ばれ、BtoBマーケ戦略を成果につなげる実践的な考え方として欠かせません。
ここでは、それぞれのステップのポイントと代表的な手法について説明します。
リードジェネレーション|はじめの“出会い”をつくる
まずはじめに大切なのが、見込み顧客との出会いをつくることです。
これがリードジェネレーションの役割です。
代表的な手法としては、
- 展示会への出展による名刺の獲得
- Web広告の運用(検索連動型/ディスプレイなど)からの資料請求
- SEOコンテンツによる自然流入
- 比較サイトやメディア掲載
などが挙げられます。
とくにBtoBでは、「単に設定を増やす」のではなく、営業につながる“質の高いリード”を集めることがポイントになります。
たとえば、「製品資料をダウンロードした人」と「ブログ記事を1回だけ読んだ人」とでは、興味の温度感が違いますよね。
つまり、ただ数を集めるのではなく、“確度の高い最初の接点”をどう設計するかが、後の成果に大きく影響してきます。
この“確度の高い最初の接点”が安定的に獲得できることで、営業活動の効率化や売上拡大につながっていきます
【関連記事】リードジェネレーションのすべて!施策の成果を高める専門知識を伝授
リードナーチャリング|“育てる営業畑”をつくる
リードを獲得したあとは、すぐに営業に引き渡すのではなく、じっくり関係性を育てていくことが大切です。
これがリードナーチャリングの役割になります。
BtoBでは検討期間が数か月〜1年を超えることも珍しくありません。
だからこそ、継続的に有益な情報を届け、「この会社、信頼できるな」と思ってもらうことが必要になります。
たとえば、
- メルマガでトレンドや事例を届ける
- ウェビナーで専門知識の共有をおこなう
- ホワイトペーパーで課題解決のヒントを渡す
といった施策が考えられます
ナーチャリングとは、言い換えれば見込み顧客を育成するために“畑を耕す”ようなものです。
つまり、丁寧に接点を重ねていくことで、商談につながるリードの“実り”を増やしていくことができるようになります。
【関連記事】リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いとは?具体例で学ぶ効果的な取り組み
リードクオリフィケーション|“渡すべき人”を見極める
ナーチャリングにより、関係が深まってきたら、いよいよ営業にパスをする段階です。
ただし、すべてのリードを営業に引き渡せばいい、ということではありません。
ここで必要になるのが、リードクオリフィケーション(見極め・選別)です。
具体的には、
- 資料ダウンロード数
- Webサイトの閲覧回数や滞在時間
- セミナーやウェビナーへの参加歴
- メール開封やクリックの有無
など、定量的な行動ログをもとに「今が声をかけるタイミングかどうか?」を判断していきます。
ここで役立つのが、いわゆる「スコアリング」と呼ばれる手法です。
点数で可視化することで、営業チームも納得感を持って動きやすくなります。
さらに精度を高めるには、マーケと営業の間でSLA(サービスレベルアグリーメント)を定義し、「どの状態のリードを、どう引き渡すか?」という基準を明確にしておくとより効果的です。
BtoBマーケティングのオンライン施策
BtoBマーケティングの世界では、今や“オンライン施策なし”では戦えない時代です。
とくに、購買プロセスの情報収集の多くが“Web上”で行われる今、オンライン上の接点づくりは欠かせません。
ここでは、BtoBマーケティングにおいて特に効果の高い代表的なオンライン施策を3つご紹介します。
コンテンツマーケティング:課題解決から信頼を生む
コンテンツマーケティングとは、見込み顧客にとって“価値のある情報”を提供することで、信頼関係を築き、リード獲得や商談化につなげていく方法です。
たとえば:
- ホワイトペーパー(課題別の解説資料)
- 導入事例やお客様の声
- ブログ記事やコラム
- 解説動画やセミナーアーカイブ
といった多様なコンテンツを、“相手の検討段階や興味関心”に応じて適切に届けていくのがポイントです。
BtoBでは、「好き」「なんとなく」といった感覚での意思決定は少なく、信頼性・専門性がものを言います。
このため、「この会社、自分たちのことわかってるな」と思ってもらえるような、“読み手目線”のコンテンツが成果のカギになります。
SEO・Web広告最適化:オンラインで“成果につながる導線”をつくる
オンライン施策の中でも、SEO(検索対策)・Web広告・LP最適化は、リード獲得の導線を設計するうえで欠かせない3本柱です。これらはバラバラに考えるのではなく、“1本の導線”として設計するのが成功のポイントです。
SEO(検索エンジン最適化)
SEOは、検索キーワードを起点に「必要な情報を、必要な人に届ける」ための施策です。
- 検索されやすいキーワードの選定
- キーワードに応じたコンテンツの設計やタイトル付け
-
内部リンクや構造、ページの読み込み速度などの技術面の調整
こうした工夫を積み重ね、Googleなどの検索から自然に流入してくる導線を増やしていきます。
BtoBではとくに、検討段階のユーザーが「◯◯ 導入 比較」「◯◯ メリット デメリット」など、課題解決に直結するキーワードで検索することが多いため、こういったキーワードを起点に、検討層向けのコンテンツを充実させると、商談化につながりやすくなります。
Web広告
一方で、スピーディに成果を出したいときや、狙った層に“ピンポイント”でアプローチしたいときにはWeb広告が効果的です。
- 検索連動型広告:ニーズが顕在化しているユーザーを狙う
- ディスプレイ広告:認知拡大やホワイトペーパーDLなどに活用
- SNS広告:LinkedIn・Facebookなどで役職・業種を絞って配信
とくにSNS広告は、業種・役職・企業規模などの条件で配信ターゲットを精密に設定できるため、ABM(アカウントベースドマーケティング)との組み合わせも効果的です。
またWeb広告は検証→改善のスピードが速いのも魅力です。仮説を立てて回しながら、成果につなげていきましょう。
ウェビナー:リアルタイムで“信頼のきっかけ”をつくる
ウェビナーは、BtoBマーケティングにおいてとても頼りになるオンライン施策のひとつです。
リアルタイムで情報を届けつつ、質問にもその場で応じられるので、“一方通行ではないつながりのある接点”をつくることができます。
コロナ禍以降、急速に広まったウェビナーですが、今や“定番施策”としてすっかり定着しています。
たとえば:
- 新サービスや機能の紹介
- 最新トレンドや業界動向の解説
- 導入事例をもとにしたパネルディスカッション
- よくある課題に対する解決策の提示
など、参加者の関心に合ったテーマ選びがカギとなります。
さらに、リアリティのある登壇者や「自分ゴト」として共感されやすい切り口のテーマを用意できると、視聴後のアクション(資料請求・商談リクエスト)につながりやすくなります。
なお、ウェビナーは、開催して終わりではなく、“終わったあと”のフォローも重要です。
たとえば、アンケートでの改善点の把握、配布資料のメール送付、興味が高い参加者への個別フォローといったアプローチは商談化の確度をグッと高めます。必ず事前に準備しておきましょう。
他にもオンラインウェビナーは、対面と比較して参加のハードルが低く、オンラインなので全国のターゲットにリーチが可能、録画やアーカイブをコンテンツとして二次活用できるといったメリットもあるため、BtoBとの相性はバツグンです。
BtoBマーケティングのオフライン施策
デジタル施策が主流になった今でも、「実際に会って話す」ことで生まれる信頼感は、BtoBマーケティングにおいて強力な武器です。とくに高単価・長期検討・複数関与者が前提となるBtoBでは、“リアルな体験”が意思決定に大きな影響を与えることも少なくありません。
ここでは、BtoBの現場で今なお効果を発揮する代表的なオフライン施策と、その活用ポイントをご紹介します。
展示会・セミナー|“直接会う価値”を最大限に活かす
展示会やセミナーは、対面でのコミュニケーションを通じて「相手に安心してもらう」ための絶好の場です。
サービスの説明やデモ、ちょっとした雑談の中にも、Webでは伝えきれない“温度感”が生まれます。
アクション例(展示会):
-
ブースでのサービス説明やデモ体験の実施
-
名刺交換からCRMへの即時登録、フォロー導線の設計
-
セミナー登壇による専門性の訴求、課題意識の高い層の集客
なお、展示会やセミナー施策を実施する際には、“イベント当日”だけでなく、“イベント後”までを見据えた設計が成功のカギを握ります。
たとえば事前準備では、ターゲットリストの作成や、DM・広告などによる集客設計、当日のブース導線の整備、説明資料やデモ機材の用意など、細かな段取りが重要です。加えて、当日の名刺・アンケート情報をすぐにデータ化し、CRMと連携させる体制づくりや、フォローアップ施策のプランニングまで含めて、全体設計する必要があります。
また、コロナ以降はオンライン施策との組み合わせや、ハイブリッド型の展示会も増加傾向にあります。たとえば「当日はブースで名刺交換、後日ウェビナーで課題を深掘り」といった流れを設けることで、オンラインとオフラインの両軸で関係性を育てることができ、より効果的なナーチャリングにつながります。
ダイレクトメール(DM)|“開封される紙”の提案力を活かす
デジタルが当たり前の今だからこそ、紙のDMには独特のインパクトがあります。
「あなただけに送られてきた」と思わせる設計ができれば、それは単なるチラシではなく、1通の“パーソナルな提案書”になります。
活用の工夫例:
-
業種・役職別にメッセージや事例を差し替えたDM
-
封筒の色や紙質を変えて「つい開けたくなる」仕掛け
-
チェックリスト形式や小冊子で保存性を高める工夫
もちろん、送って終わりではなく、成果を高めるための工夫も必要です。
たとえば、連動導線の設計では特設LPへのQRコード/Webフォームと連携したり、フォロー施策では DM到着時期に合わせて担当営業による電話でのフォローを行う、またナーチャリング活用では DLや反応データをMAでスコア管理するといったことが挙げられます。
なお、DMは、ターゲットを絞って少数に、丁寧に届けるという点において ABM(アカウントベースドマーケティング)との相性もよい施策と言えます。
テレマーケティング|声で“温度感”を読み取り、関係性を深める
テレマーケティングは、単なる「アポ取り」ではなく、見込み顧客の状況を“声”からニーズを読み取る重要な手段です。
BtoBにおけるテレマはむしろ、課題のヒアリングやナーチャリングの一環として活用するケースが増えています。
代表的な用途:
-
資料請求者へのニーズや現状課題のヒアリング
-
ウェビナー参加者への個別フォロー
-
DM到着後や広告への反応確認と興味度合の測定
- 製品検討状況の把握(競合の利用有無など)
テレマーケティングにおいて成果を上げるためには、顧客像に合わせたスクリプトの設計と柔軟な応対トレーニングやトーク内容の記録と改善サイクルの構築、また営業/マーケ間でのリード評価基準の統一(SLAなど)といった取り組みも重要です。
さらにテレマーケティングは、他の施策と組み合わせてこそ真価を発揮します。
たとえば「ホワイトペーパーのダウンロード → メール配信 → テレマーケティング」といったステップで取り組むことで、見込顧客の反応を段階的に可視化し、ニーズを把握したうえで営業への引き渡しを行うことができます。
【関連記事】BtoBマーケティングの主な施策7選!オンライン・オフラインごとの戦略について徹底解説
ABM(アカウントベースドマーケティング)の活用
ABMは、「この企業にこそ導入してほしい」という重点顧客にピンポイントでリソースを集中する戦略です。
BtoBの営業・マーケティング活動では、「どれだけ多くの人にアプローチできたか?」以上に、「本当に狙いたい企業に、どれだけ深く入り込めたか?」が重要になることも多いです。
ABMはそんな場面にピッタリの考え方であり、導入企業も年々増えています。
ABMの基本と導入ステップ
ABMは、あらかじめ選定した「狙いたい企業=アカウント」に対して、最適化されたマーケティング施策を展開する手法です。“企業単位のパーソナライズ戦略”と捉えるとイメージしやすいかもしれません。
導入のステップは次の通りです:
-
ターゲット企業の選定
- 業種/規模/売上/決裁構造などから「理想的な顧客像」を定義
例:ARR(年間売上)1億円以上/製造業/従業員500名以上…など -
営業とのすりあわせ
- マーケと営業で「この会社を狙う理由」「突破口はどこか」を共有
- リード情報/担当部署/過去接点の整理などもあわせて実施 -
アカウント別の施策設計と実行
例:
- A社向け:業界課題に特化したセミナーの案内
- B社向け:個別ROI試算付きの提案資料
- C社向け:役職者宛てDM+専用ランディングページ個別施策の設計と実行 - アカウント単位で効果測定と改善
- 各社のアクション履歴、開封・閲覧データ、営業ヒアリング結果を統合し、次の一手へ活用
ABMのいいところは、リソースを“分散させずに集中投下できる”ため、受注率やLTV向上に直結しやすいことです。
導入初期は対象を絞り、小規模から始めることで、より密度の高い提案やサポートが実現できます。
【関連記事】ABMとは?基礎知識から実践の流れまで徹底解説
ABM成功のためのポイント
ABMをうまく機能させるには、いくつかのコツがあります。
ここでは、うまくいっている企業が実践している、3つの重要なポイントをご紹介します。
1.営業との“本当の連携体制”をつくる
ABMは、マーケティング単体では成り立ちません。
営業とマーケが1つのチームとしてターゲット企業に向き合う体制が必要不可欠です。
たとえば、
-
アカウントごとの進捗を定例で共有
-
営業が得た情報(関心テーマ・社内構造など)をマーケ施策に反映
-
マーケ側がMAや広告の行動データを営業が商談・提案に活用
といったように、営業とマーケの間で「情報の行き来」の活発な状態をつくれるかが、成果を左右します。
2. ターゲット企業を徹底的に“読み解く”
ABMでは1社1社に合わせた提案を行うため、「この企業のリアルな課題は何か?」を徹底的に調べる必要があります。
- 業界の構造や法規制
- 競合の動きや既存ツールの有無
- 導入ハードル(稟議・社内政治・予算)
こういった情報を事前に把握し、「だからこそこの提案が刺さる」という納得感のあるストーリーを描けるかどうかがカギです。
これにより、「なんだか自分たちのことをよくわかってくれてるな」と思ってもらえる状態が生まれます。
3.“パーソナライズ”された提案と接点の工夫
ABMでは、汎用的なコンテンツ「誰でも使える資料」ではなく、ターゲット企業の事情にぴったり合った体験設計が求められます。
たとえば、
- 導入企業と同じ業界の事例を用いたホワイトペーパー
- 特定業務にフォーカスしたROI試算資料
- 関係者別の個別メール文面・ウェビナー登壇者選定
など、“あなたの会社に合わせました”という細やかさが成果につながります。
【関連記事】ABM戦略完全ガイド!主要なメリットと実践ステップ
ABMは“選んで、集中して、深く届ける”マーケ戦略
ABMは「広く浅く」ではなく、「狭く深く」を地道に攻める戦略です。
展示会やセミナーといった大量のリードを集める施策とは異なり、少数の企業と本質的な関係を築くことにリソースを集中させるアプローチです。
そしてその分、受注率や顧客単価、LTV(顧客生涯価値)の最大化に直結しやすく、営業との連携も深まるため、マーケティングの存在意義も高まります。
マーケティングが分散しがちな今だからこそ、ABMという“選択と集中”の視点を、あらためて戦略の柱に据えてみるのはいかがでしょうか。
【関連記事】ABM戦略完全ガイド!主要なメリットと実践ステップ
KPI設計と効果測定
マーケティング施策を進めていくうえで欠かせないのが、「ちゃんと成果が出ているのか?」を定期的に確認し、改善していくことです。そのためには、KPIを適切に設計し、施策ごとの進捗やインパクトを見える化しておく必要があります。
ここでは、BtoBマーケティングにおける代表的なKPIと、改善につなげるためのPDCAの考え方について解説します。
BtoBマーケティングにおける主なKPI
BtoBマーケティングでは、「リードを獲得して終わり」ではなく、その後の育成・商談・受注までが一連の流れとして設計されます。そのため、KPIもフェーズごとに切り分けて考えるのがポイントです。
以下はよく使われる代表的な指標です。
マーケ起点(TOFU)
| 主なKPI例 | リード数、資料DL数、セミナー参加数 |
|---|---|
| 補足 | 見込み顧客の“入口”部分のボリュームを測定 |
商談起点(MOFU・BOFU)
| 主なKPI例 | 商談化率、営業引き渡し数 |
|---|---|
| 補足 | ナーチャリングやクオリフィケーションの成果を評価 |
成約起点(営業連携)
| 主なKPI例 | 受注率、平均受注額、LTV |
|---|---|
| 補足 | 営業と連携しながらマーケ施策が売上にどれだけ貢献したかを見る |
共通KPI
| 主なKPI例 | 案件創出数、リードから受注までのリードタイム |
|---|---|
| 補足 | マーケ&営業で共通管理することで連携が強化される |
たとえば、
- 「リードは取れているのに、商談化率が低い」なら、ナーチャリング施策の見直しが必要かもしれません
- 「商談にはなるけど、受注に結び付かない」なら、リードの質や営業引き渡しのタイミングがずれている可能性があります
KPIは“単なる数字の羅列”ではなく、施策の方向性と連動した「評価のモノサシ」です。誰が、どこを見て判断するのかを明確にしながら設計していきましょう。。
【関連記事】BtoBマーケティングにおけるKPI設定ガイド!目標達成に向けたアプローチを最適化しよう!
PDCAサイクルと改善手法
KPIを設定したら、あとは“回し続けること”が大事です。
ここで活用したいのがPDCA(Plan-Do-Check-Act)の考え方です。
ただし、PDCAは単なる形式的な「繰り返し」ではなく、“仮説→検証→改善”という戦略的な意思決定のループとして捉えることがポイントです。
たとえば
- Plan(計画)
→ SEOコンテンツでホワイトペーパーDLを月50件目指す - Do(実行)
→ 検索ボリューム調査に基づき3記事を公開 - Check(検証)
→ 流入数は順調だが、CVR(DL率)が2.1%と想定より低い - Act(改善)
→ DL導線の位置やCTA文言を見直し、ABテストを実施
このように、数字をもとに判断し、次の打ち手を調整することで、施策の質がどんどん高まっていきます。
また、注意したいのは「KPIに振り回されて本質を見失うこと」です。
- 目的のない数字改善(例:DL数のための“バラマキ施策”)
- 測定のしやすさだけで指標を選ぶ(例:CVRだけ見る)
といった状態にならないように、「このKPIは、何のために、誰が使うのか?」を常に意識することが大切です。
PDCAを高速で回せる体制が整ってくると、マーケティング組織としての柔軟性も上がり、環境変化への対応力や、新施策への適応力がぐんと高まります。
まとめ
ここまで、BtoBマーケティングの戦略について、以下のポイントを中心に解説してきました。
- BtoBマーケティング戦略の基本プロセス
- BtoBマーケティングのオンライン・オフライン施策
- ABMの活用
- KPI設計と効果測定
マーケティングでは、「すぐに成果が出る施策」を求めたくなってしまうこともありますが、戦略的な設計・施策の連携・検証の継続といった、地に足のついた取り組みがとても重要になります。そして何より、「この企業にとって、自分たちはどんな価値を提供できるのか?」を常に問いながら、マーケティング活動を組み立てていくことが成果への近道です。
ただ施策を並べるのではなく、「なぜそれをやるのか?」「誰に、どんな変化をもたらすのか?」という視点を常に持つことが、成果につながる力になります。
『猿人』では、戦略の立案から具体的な施策の実行、成果の検証・改善に至るまで一気通貫でのBtoBマーケティング支援を行っています。
- 「何から始めればいいかわからない」
- 「社内で施策がバラバラで…」
- 「営業とマーケの連携がうまくいかない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
展示会やセミナー、カンファレンスなどのTodoリストと進行表、RFPの書き方をまとめたDLコンテンツを下記にて公開中です、ぜひこの機会にご覧ください。
メソッドブログ関連記事
- BtoBマーケティングとは?効果的な戦略立案の方法と主要施策を紹介
- リードジェネレーションのすべて!施策の成果を高める専門知識を伝授
- リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いとは?具体例で学ぶ効果的な取り組み
- BtoBマーケティングの主な施策7選!オンライン・オフラインごとの戦略について徹底解説
- ABMとは?基礎知識から実践の流れまで徹底解説
- ABM戦略完全ガイド!主要なメリットと実践ステップ
- BtoBマーケティングにおけるKPI設定ガイド!目標達成に向けたアプローチを最適化しよう!