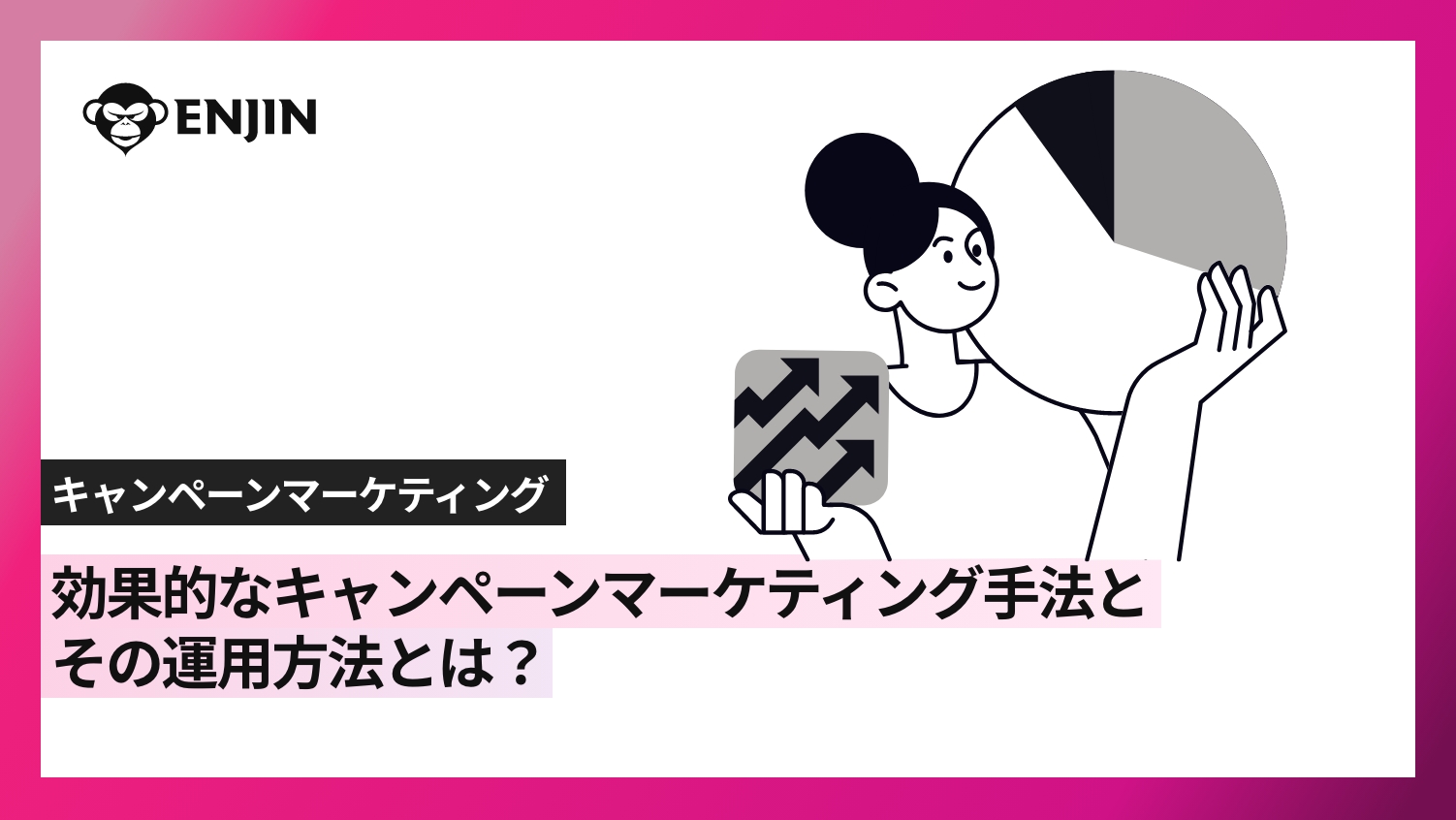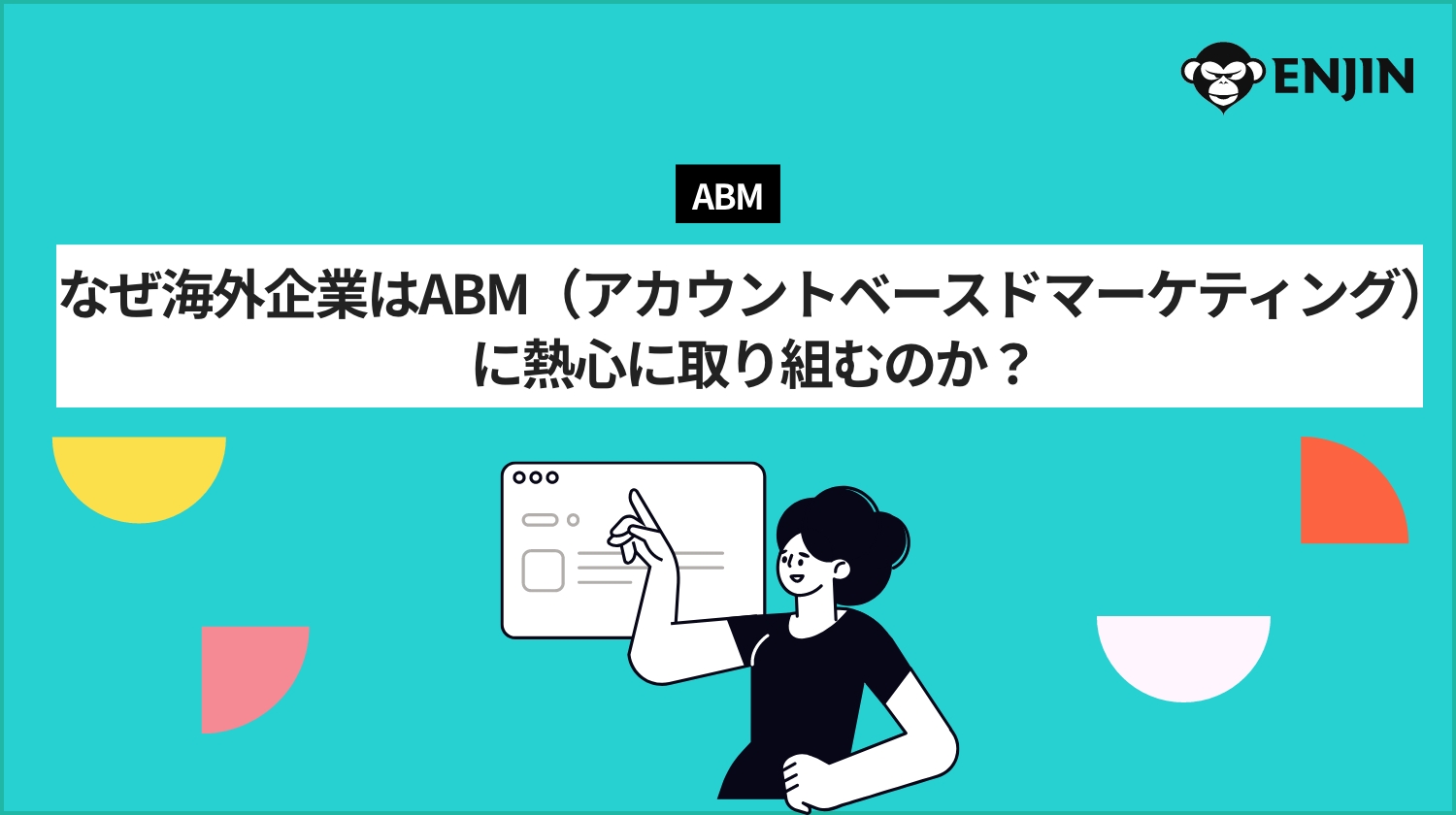リードナーチャリングとは?実践するメリットと成功するためのステップ
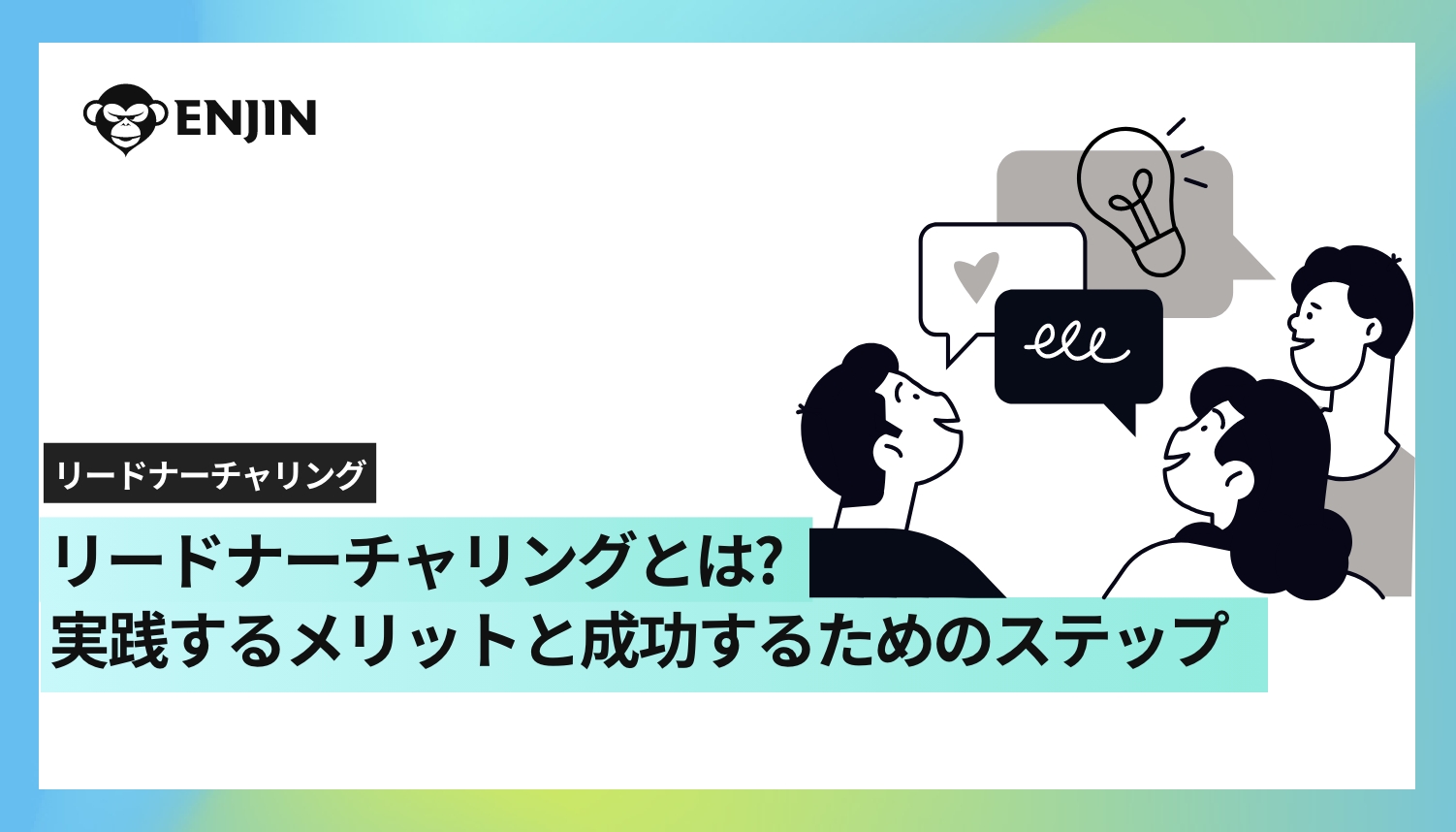
BtoBマーケティングでは、リード獲得後の育成「リードナーチャリング」こそが成果を左右する重要なプロセスです。
とはいえ、日常的にリードナーチャリングという言葉自体は耳にしながらも、「実際のプランニングにどう落とし込んでいけばよいのか、正直よくわからない・・」と悩まれている方もおられるかもしれません。
そこで、本記事では、リードナーチャリングの基本から得られるメリット、実践のためのステップ、代表的な手法までをわかりやすく解説します。
リードナーチャリングの基礎知識
BtoBマーケティングにおいてリードナーチャリングは、見込顧客を段階的に育成し、商談や受注につなげるための重要な活動となります。
まずは、リードナーチャリングの基本と、リードジェネレーションとの違いについて解説していきます。
リードナーチャリングとは
リードナーチャリングとは、さまざまな営業・マーケティング活動を通じて獲得した見込顧客に対し、継続的に情報の提供やコミュニケーションを行い、関心度合を高めていくマーケティング活動です。
BtoBの意思決定プロセスは、複雑で長期化しやすい傾向にあるため、段階的な育成活動を通じて自社の製品・サービスへの興味関心を醸成する活動が不可欠となります。
見込顧客の検討フェーズや課題に合わせて、最適なコンテンツと接点を設計することが、成果につながるポイントです。
リードナーチャリングとリードジェネレーションの違い
リードジェネレーションとは、新たな見込顧客を獲得する活動、リードナーチャリングは既存リードを育成する活動です。
この2つは密接に関連しており、リードジェネレーションで得たリードをナーチャリングによって育成し、最終的に商談化・受注につなげるという流れとなります。
効果的に組み合わせることで、マーケティング活動の効率化と営業成果の最大化が実現できます。
【関連記事】リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いとは?具体例で学ぶ効果的な取り組み
リードナーチャリングがもたらす主なメリット
リードナーチャリングを実践することで、見込顧客の離脱防止や営業活動の効率化、新規開拓コストの削減、そして信頼関係の構築といった多くのメリットを教授できます。
ここでは、主なメリットについて解説します。
見込顧客の離脱防止と営業効率化
リードナーチャリングを実施すると、見込顧客が他社へ流出するリスクを減らし、適切なタイミングで営業に引き渡すことで営業活動の効率化が図ることができます。
ナーチャリングによる継続的なフォローを行わないと、せっかく獲得した見込顧客が競合に流れてしまう可能性があります。
たとえば、セグメント別のメルマガ配信したり、ウェビナーを案内したりすることで、顧客とのつながりを保ちつつ、商談化のチャンス創出の最大化を目指しましょう。
新規顧客開拓コストの削減
新規リードの獲得コストは既存リードの育成に比べて高くなる傾向にあるため、リードナーチャリングを活用することで新規開拓の負担やコストを削減していくことが必要です。
いまあるリードや、しばらく接点のなかった休眠顧客の再活性化することでも、効率的に売上アップを図ることができます。
再アプローチするための特別なオファーメールや、パーソナライズドされたコンテンツの提供などを行い、既存リードの価値を最大化しましょう。
顧客との信頼関係・ブランドイメージの向上
BtoBマーケティングにおいても「この会社なら安心できる」と思ってもらえる信頼関係の構築やブランドの印象は、購買決定に寄与する要素となります。
定期的に情報を届けることで接点を保ち、やりとりを重ねることで、自然に顧客との信頼関係が深まり、自社のブランドやサービスへの好感度が向上します。
これには、導入事例や成功事例の定期配信、SNSやコミュニティを活用した双方向コミュニケーション、導入後のアフターサポートに関するご案内やアップセルの提案などを通じて顧客との関係性を深めることが重要です。またこれらの活動は、見込顧客だけでなく、既存顧客のLTV(顧客生涯価値)の向上にも寄与します。
リードナーチャリングの実践ステップ
リードナーチャリングを成果につなげるには、戦略的な設計と、段階を踏んだ着実な実行が不可欠です。
ここでは、実践のための主要ステップを解説します。
①ターゲット設計とペルソナの明確化
リードナーチャリングの精度は、ターゲット設定の明確さに大きく左右されます。顧客の属性やニーズを具体的に捉えることで、より適切なコンテンツと接点設計が可能となり、成果に直結します。
もし、ターゲットが不明確なまま施策を進めてしまうと、リードの反応率が下がり、機会損失やリソースの浪費につながるリスクもあるため、最初の設計段階をしっかり押さえることが重要です。
②リードのセグメンテーションとスコアリング
リードの属性や行動履歴、興味関心などを基にセグメントを分類し、購買意欲を数値化する「スコアリング」を組み合わせることで、より最適なタイミングと内容でアプローチを行うことが可能になり、営業活動の効率化や商談化率の向上が期待できます。
ただし、セグメントの粒度がざっくりしすぎるとパーソナライズ性が欠け、細かすぎると運用負荷が高まるなどのリスクがあるため、最適な設計バランスが求められます。
③コンテンツ設計とチャネル選定
見込顧客の課題や検討フェーズに応じて、適切なコンテンツを設計し、メール・SNS・ウェビナーなど最適なチャネルを選定することが、リードナーチャリングの効果を高める鍵となります。
各チャネルの特性を活かした情報発信により、リードとの関係性を段階的に深めることが可能です。
一方で、チャネルの選定ミスや配信のタイミング・頻度が不適切だと、せっかくの接点も機会損失につながる恐れがあるため、運用設計の精度が問われます。このため、チャネル設計は慎重に、相手目線で考えるのがポイントになります。
リードナーチャリングの主な手法
リードナーチャリングにはさまざまな手法があり、ターゲットや目的に応じて最適な施策を選択することが重要です。
ここでは、代表的なリードナーチャリングの手法を紹介します。
メールマーケティング
メールは、リードナーチャリングにおける中心的な手法のひとつです。
定期的なメルマガや、検討フェーズに応じたパーソナライズドなステップメールを通じて、顧客の関心を段階的に高め、関係性を深めていくことが可能です。
とくに、メールは顧客の属性や検討状況に応じて内容や配信タイミングを柔軟に調整できる点が大きな強みです。
やみくもに送るのではなく、「誰に」「何を」「いつ」届けるかを丁寧に考え、配信設計することでリードの育成を着実に進め、商談化へのスムーズな移行をサポートすることができます。
ウェビナー・セミナーの活用
ウェビナーやセミナーは、双方向のコミュニケーションと大規模な情報提供を同時に実現できるため、リードナーチャリングにおいて非常に効果的な施策です。
オフラインイベントに比べてコストを抑えられるだけでなく、参加者の関心度を高めやすく、コンバージョンへの移行を後押しします。また、リアルタイムでの質疑応答やアンケートを活用することで、顧客理解を深めながら、次のアクション設計にもつなげることができます。
SNS・オウンドメディア・ホワイトペーパー活用
SNSや自社メディア、ホワイトペーパーは、幅広い見込顧客に対して価値ある情報を提供し、ブランド認知や信頼構築につなげる重要なチャネルです。
とくにホワイトペーパーは、検討段階にあるリードとの接点構築として有効であり、ダウンロード後のフォローアップまできちんと導線設計しておくことで、ナーチャリングの効果が格段に向上します。また、SNSやオウンドメディアを通じた定期的な情報発信により、潜在層や関心層との接触機会をとのつながりを絶やさないようにすることも大切です。
【関連記事】BtoBにおけるコンテンツマーケティングとは?効果的な活用方法と主な種類
まとめ
この記事では、リードナーチャリングについて以下の内容で解説しました。
- リードナーチャリングがもたらす主なメリット
- リードナーチャリングの実践ステップ
- リードナーチャリングの主な手法
リードナーチャリングは、BtoBマーケティングにおいて見込顧客を段階的に育成し、「ちょっと気になるかも」と思ってくれた見込顧客を、自然な形で商談・受注へとつなげていくための大事な取り組みになります。
ターゲット設計やセグメンテーション、コンテンツ設計、チャネル選定などを戦略的に行うことで、見込顧客の離脱を防いだり、営業の動きをスムーズにしたり、新規開拓コストを抑えたりと、多くのメリットを享受できます。
メールやウェビナー、SNSなど多様な手法を組み合わせ、顧客ごとの最適なアプローチを実践しましょう。
『猿人』 では、BtoB IT企業を中心に、豊富な経験とノウハウを活かしたマーケティング支援を提供しています。
リードジェネレーションからリードナーチャリングまで、各段階に合わせて最適な施策を組み合わせ、見込顧客の育成から成約までを一貫してサポートできるのが強みです。
リード獲得施策に関連するコンテンツ制作のTodoリストや進行表、RFPの作り方に関するDLコンテンツを下記にて公開していますので、ぜひこの機会にご覧ください。