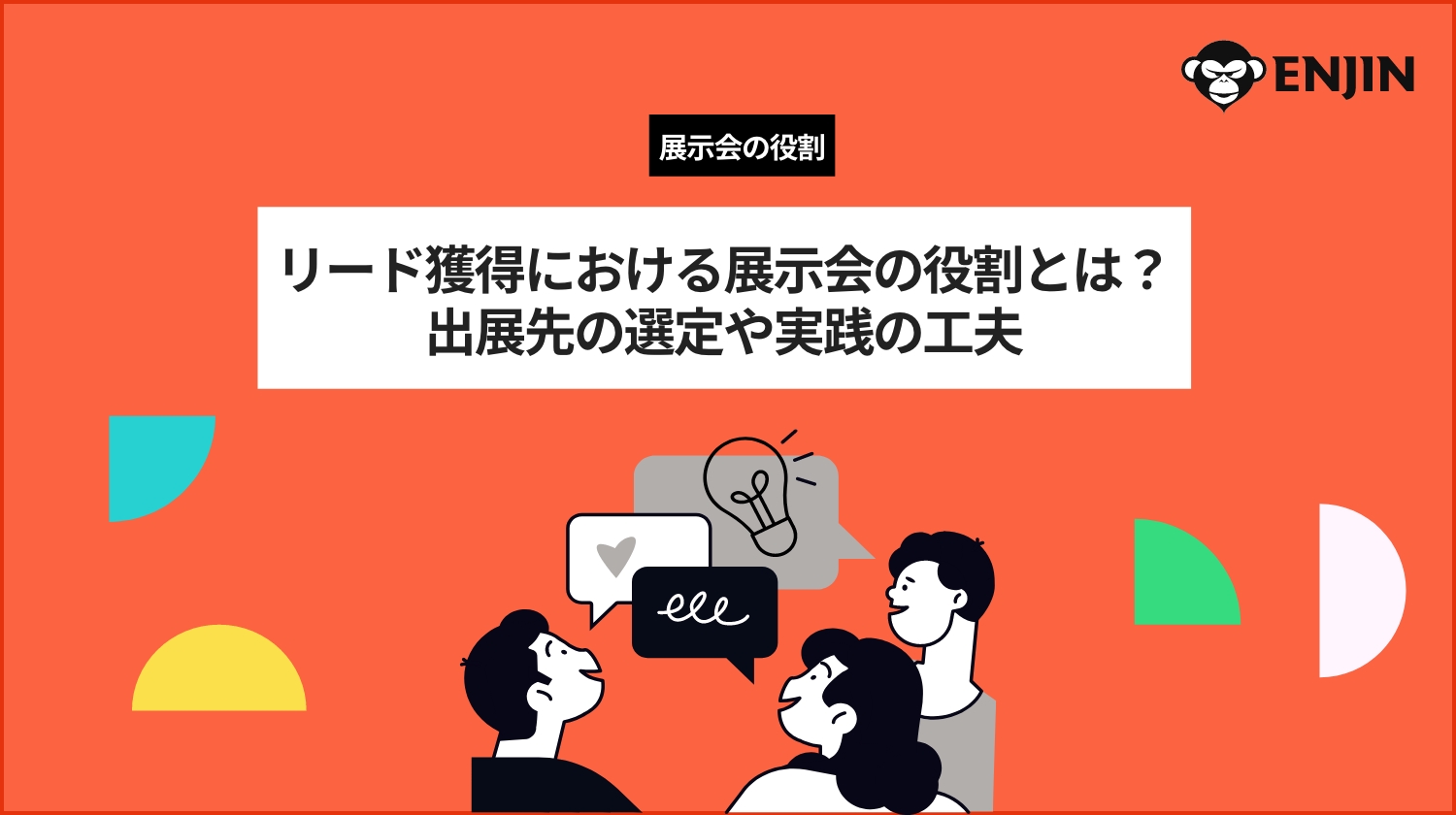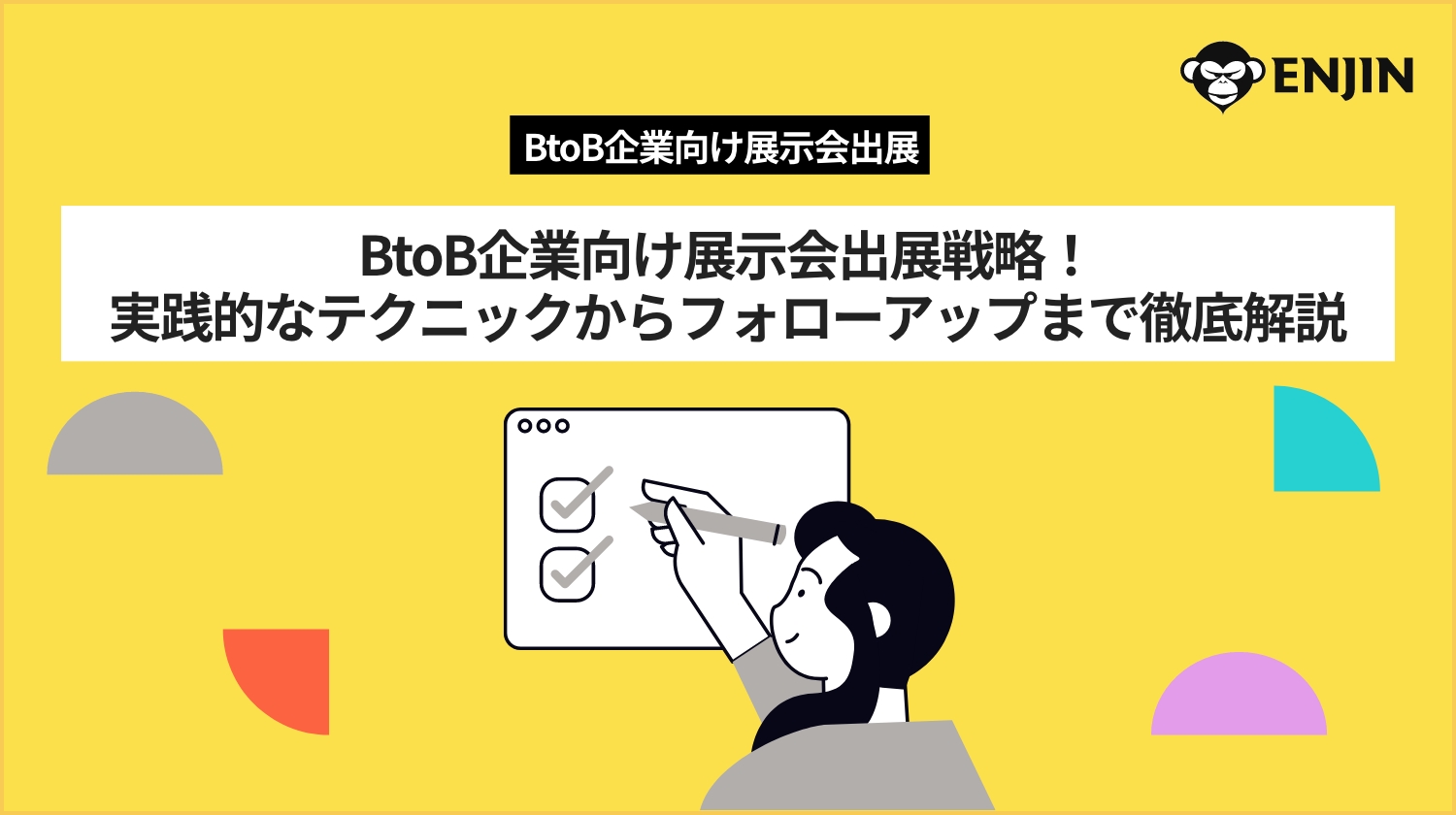BtoBにおけるリードナーチャリング施策の全体像!主要な方法をカテゴリ別に紹介

「展示会で名刺をたくさん集めたのに、いつの間にかメルマガをオプトアウトされて送れなくなっていた……」
「Webサイトからの問い合わせが来ても、結局『検討中』や『情報収集』で終わってしまう……」
——このように、せっかく獲得したリードが気づいた頃には「使えないリード」になってしまっているケースは少なくありません。
「見込み客は増えているのに、なかなか売上に直結しない」「アポにはつながるけれど、検討フェーズが浅すぎて商談化しない」といったお悩みを感じている方もいるのではないでしょうか。
とくににBtoBビジネスでは、リード獲得の次のステップ、つまり「継続的な関係づくり」が成果に大きく影響します。
そこで今回は、BtoBにおけるリードナーチャリング施策の全体像を整理しつつ、実際に使える主要なアプローチ方法をカテゴリ別にわかりやすく解説します。「やったほうがいいのはわかっているけれど、どこから着手すべきかわからない」そんな方にお読みいただきたい内容です。
リードナーチャリング施策とは
「リードナーチャリング」という言葉は耳にしたことがあっても、「具体的にどんなことをするのか」と聞かれると、自信を持って説明できない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、まずはリードナーチャリングの基本的な定義と、なぜBtoBマーケティングにおいて重要なのかについて解説します。
【関連記事】リードナーチャリングとは?実践するメリットと成功するためのステップ
リードナーチャリングの定義
リードナーチャリングとは、見込み顧客(リード)に対し、継続的な情報提供や適切なタイミングでのコミュニケーションを通じて、購買意欲を育てていくマーケティング施策です。
とくにBtoBビジネスでは、このナーチャリングの考え方が非常に重要になります。なぜなら、BtoBの購買意思決定には時間がかかり、初回接触から導入まで平均6ヶ月から1年以上かかることも珍しくないからです。
つまり、「リードを獲得したら終わり」ではなく、そこから始まる長期的な信頼構築プロセスにこそ、成果を出すための本質があります。
そのため、リードナーチャリングでは、次のようなアプローチが基本となります。
- 見込顧客がどのフェーズにいるのかを見極める
- 見込顧客のフェーズに合った情報を適切なチャネルで届ける
- 見込顧客と継続的な接点をつくり、自然に次のアクションへ進んでもらう
【関連記事】リードジェネレーションとリードナーチャリングの違いとは?具体例で学ぶ効果的な取り組み
リードナーチャリング施策の重要性
BtoBの購買プロセスは、年々複雑化・長期化しています。多くの見込み顧客が、営業と接触する前にWeb検索や比較サイトで情報を集め、判断材料を整えるのが実情です。つまり、見込み顧客の意思決定の大部分は、営業と接触する前に進んでいます。
そんな時代だからこそ、リードナーチャリングが果たす役割はとても大きく、
そんな時代だからこそ、リードナーチャリングが果たす役割は非常に大きく、次の働きによって「いざ、本格的に検討を!」という時に自社の製品・サービスを第一想起してもらえるようにする必要があります。
- 検討中のタイミングで「有益な情報」を届ける
- 親しみや信頼感を積み重ねる
- 顧客の記憶の中に「頼れる存在」として残る
このようなアプローチを着実に行っておけば、導入意欲が高まったタイミングで「あの会社に相談してみよう」と声をかけてもらえる可能性がぐっと高まります。
結果として、
- 受注率の向上
- 顧客生涯価値(LTV)の拡大
- 新規リード獲得コストの削減
といった、営業・マーケ双方にとってのプラス効果も期待できます。
【関連記事】リードナーチャリングとは?実践するメリットと成功するためのステップ
リードナーチャリング施策の全体像
効果的なリードナーチャリングを実現するには、「リードを獲得したら、とりあえずメルマガを送る」といったような場当たり的な対応ではなく、しっかりとした戦略的な段階的アプローチが必要です。
ここでは、リードナーチャリング施策を進める上での全体的な流れとポイントを、5つのステップに分けて解説します。
1.リード情報のデータベース化
リードナーチャリングの最初のステップは、見込み顧客の情報をきちんと整理し、一元管理することです。
展示会での名刺交換、Webサイト経由の資料請求、セミナー参加など、さまざまなチャネルからリードは入ってきます。それらがバラバラな場所に保存されていたり、重複や抜け漏れがあったりすると、正しい施策は打てません。
展示会での名刺交換、Webサイトからの資料請求、セミナー参加など、リードの獲得チャネルは多岐にわたります。これらの情報がバラバラに保存されていたり、重複や抜け漏れがあったりすると、効果的な施策は打てません。包括的な顧客データベースを構築することが、リードナーチャリング成功の土台となります。
CRMやMAツールを活用しながら、以下の点を意識してデータベースを整備しましょう。
-
情報の重複を排除し、常に最新状態を保つ
-
フォーム入力データや行動履歴も記録に含める
-
リード獲得チャネルごとの傾向を分析可能にする
正確なデータベースが整うことで、「誰に、いつ、どんな情報を届けるか」という施策の設計が進めやすくなります。
2.ターゲット理解とセグメント分け
次に、リードの属性や行動に基づいたグルーピング、すなわちセグメント分けに取り組みます。
たとえば、以下のような切り口でリードを分類できます。
-
業種・業界・企業規模
-
部署や役職などの役割
-
Webサイトの閲覧履歴や資料ダウンロード状況
-
商談化までのスピード感や関心テーマ
これにより、「今どの段階にいる誰に、どんな情報を届けたら良いか」が明確になります。
たとえば、まだ情報収集中の方には基礎的な教育コンテンツを、すでに比較検討している方には類似業界の導入事例を紹介するなど、セグメントごとに最適な施策を打ち分けられるようになります。
3.カスタマージャーニーの設計
次に、リードがどのようなステップを経て顧客になるのかを可視化する「カスタマージャーニー設計」を行います。
BtoBの購買意思決定は複数人で行われるケースが多く、検討フェーズが長期化しやすいのが特徴です。そのため、以下のようなフェーズごとにお客様の心理状態と必要な情報を整理しておくことが重要です。
- 認知フェーズ:顧客が自身の課題に気づき、解決策を探し始める段階。
- 関心フェーズ:具体的な手段やサービスを比較・検討し始める段階。
- 意思決定フェーズ:導入するパートナーを選定し、商談化へ移行する段階。
さらに、MQL(Marketing Qualified Lead:マーケティングが認定した有望なリード)からSQL(Sales Qualified Lead:営業が認定した有望なリード)への移行基準をマーケティングと営業の間で共有しておくことで、リードを引き渡すタイミングでの「ズレ」を防ぎ、ナーチャリングの成果を無駄にしない運用体制が構築できます。
4.フェーズに応じた施策の実行
カスタマージャーニーを描いたら、いよいよ実際の施策をフェーズごとに実行していきます。
-
初期フェーズ(認知・情報収集段階):
業界動向レポートや課題提起型のコラムなどで「興味喚起」を促します。ここでは、まだ具体的なソリューションを探している段階ではないため、顧客が抱えるであろう潜在的な課題を提示し、気づきを与えるコンテンツが有効です。 -
中間フェーズ(情報収集・比較検討段階):
セミナー案内や比較資料を提供して「深掘り促進」を図ります。自社のソリューションがどのように顧客の課題を解決できるのか、競合との違いは何かなど、より具体的な情報を提供し、理解を深めてもらいます。 -
後期フェーズ(意思決定段階):
導入事例や価格ガイドなど、「最終判断材料」を提供します。実際に導入を検討している顧客に対して、具体的な成功事例や費用に関する情報を提供し、購買を後押しします。
「今この人は、どの段階にいて、どんな情報が欲しいのか?」
ここを意識した施策設計が、“タイミングのズレ”による離脱を防ぐカギになります。継続的な接点の構築を通じて、少しずつ信頼と関心を積み上げていきましょう。
5.効果測定とプロセス改善
リードナーチャリング施策において、最後かつ最も重要なのが、効果測定とPDCAサイクルの実行です。
以下の指標などを活用し、「どの施策が、どのセグメントに効いているのか」を振り返ります。
- メール開封率/クリック率:メールコンテンツへの関心度や効果を測ります。
- コンテンツの閲覧数・滞在時間:提供したコンテンツへの興味度合いや深掘りの度合いを測ります。
- フォーム経由の反応率や商談化率:リードが次のアクションへ進んだ割合や、営業へと引き渡されたリードの質を測ります。
これらのデータから見えてきた仮説をもとに、訴求軸や情報提供のタイミング、使用するチャネルなどを調整しながら改善サイクルを回していくのが理想です。
KPIを設定せずにやみくもに施策を重ねるのではなく、データを活かして再現性のある仕組みに育てていくのが、リードナーチャリング成功のポイントです。
リードナーチャリングの主要施策
リードナーチャリングには多種多様なアプローチがありますが、「どれを選べばいいんだろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
ここでは、多くの企業で活用されている代表的な施策を、以下の3カテゴリに分けてご紹介します。
- オンライン施策
- オフライン施策
- コンテンツ提供
それぞれの特徴とおすすめの活用シーンを一覧にまとめながら、実践で使える視点をお届けします。
オンライン施策
デジタルチャネルを活用したオンライン施策は、スピーディかつ効率的に見込み客と接点を持てるのが特徴です。自動化やスコアリングも組み合わせると、温度感に応じたコミュニケーションが可能になります。
メールマーケティング
| 特徴 | 定期的な情報提供と個別対応が可能 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | すべてのフェーズで活用可能 |
SNS運用
| 特徴 | リアルタイムな情報発信とライトな接点創出 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 認知・関心を高めたい段階 |
ウェビナー開催
| 特徴 | 専門知識の共有と直接的な関係づくりによる信頼構築 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 検討段階のリードへのアプローチに最適 |
Web広告
| 特徴 | 狙ったターゲットへの効果的なリーチ |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 認知拡大・再訪問促進 |
オウンドメディア
| 特徴 | SEO効果を活かして継続的な流入が見込める |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | すべてのフェーズで活用可能 |
とくにメールマーケティングは、セグメントに合わせたステップ配信ができるため、温度感を見極めながら継続的な育成が可能です。
また、ウェビナーはリアルな接点を持ちにくいBtoB領域でも、“顔の見える信頼構築”ができる有効な手段として支持を集めています。
オフライン施策
リアルでのやり取りを通じて、深い信頼関係や温度感を直接つかめるのがオフライン施策の強みです。とくに、導入までの意思決定に関与する人数が多いBtoBでは、「人」の信頼感が後押しになるケースも少なくありません。
展示会
| 特徴 | 見込み客との出会いの母数が多く、網羅的に接点が取れる |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 認知・初期関心のフェーズ |
対面セミナー
| 特徴 | 深い専門知識の共有による信頼関係の構築 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 検討フェーズにいるホットリード向け |
テレマーケティング
| 特徴 | 個別ニーズのヒアリングと相手の反応に応じた柔軟な対応が可能 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | すべてのフェーズで活用可能 |
DM(ダイレクトメール)
| 特徴 | 物理的なインパクトと特別感の演出 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 特定ターゲットや決裁者への訴求に有効 |
なかでもテレマーケティングは、オフライン施策でありながらも場所にとらわれず、相手の声のトーンやリアルタイムの反応から温度感を測れるという点で、デジタルにはない貴重な接点になります。
また、DMは少しアナログな施策でありながらも、あえて物理的な手段を使うことで印象に残るという効果が期待できます。
コンテンツ提供
価値のある情報を提供し続けることで、「この会社は頼れる存在だ」と思ってもらえるのがコンテンツ施策の醍醐味です。検討初期から後期まで、段階に応じて必要な情報を届けられる柔軟性の高さが強みです。
ホワイトペーパー
| 特徴 | 専門性の高い調査や解説資料、業界動向の提供で信頼獲得 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 認知・検討段階 |
事例紹介
| 特徴 | 具体的な成功事例による信頼性向上 |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | 検討・決定フェーズ |
eBook
| 特徴 | 包括的かつ体系的に学べるナレッジ |
|---|---|
| おすすめの活用場面 | すべてのフェーズで活用可能 |
ホワイトペーパーは、とくに情報収集段階のリードに対して「まずは読み物から入ってもらう」導線として効果的です。
一方、事例紹介は商談前後のタイミングで渡すことで、「他社の成功体験」が検討を後押しする材料になります。
【関連記事】リードナーチャリングの成功事例3選!具体的なケースや主な施策を解説
各施策には強みと適したタイミングがあります。
リードの検討フェーズに応じて、オンライン×オフライン×コンテンツを“掛け算”で組み合わせることが、ナーチャリングを成功させるコツです。
まとめ
この記事では、BtoBマーケティングにおけるリードナーチャリング施策について、以下のポイントを中心に解説してきました。
- リードナーチャリング施策の定義と重要性
- リードナーチャリング全体の流れ(データ整備から改善まで)
- オンライン・オフライン・コンテンツ施策の具体例
リードナーチャリングは、単なるメール配信やコンテンツ提供ではありません。
見込み客の方と信頼関係を築きながら、購買へと導いていく“育成のプロセス”そのものです。
とくにBtoBの領域では、意思決定に至るまでの時間が長く、関わる人も多いからこそ、リードと丁寧に向き合い、適切な情報を適切なタイミングで届けることが求められます。
そのためには、
- リード情報の一元管理
- セグメントごとのコミュニケーション設計
- カスタマージャーニーに沿った施策実行
- 効果測定と改善
といったステップを“戦略的かつ継続的”に実行していくことが不可欠です。
オンライン・オフライン・コンテンツ施策を柔軟に組み合わせながら、お客様に「この会社は信頼できる」と思ってもらえるような体験を提供していきましょう。
「戦略的なリードナーチャリングを始めたい」そんなあなたへ
『猿人』では、戦略設計から施策の実行、KPI設計、組織づくりまでトータルで支援しています。
こんなお悩みありませんか?
- 「リードナーチャリング施策の全体設計がわからない」
- 「獲得したリードの効果的な育成方法が見つからない」
- 「施策の効果測定やPDCAサイクルの回し方に悩んでいる」
このようなお悩みを持たれる方は、まずはお気軽にご相談ください。
また『猿人』がご提供する、リード獲得からナーチャリング、営業連携までの実践ノウハウを詰め込んだ資料が以下よりダウンロードいただけます。
ぜひこの機会にご覧ください。