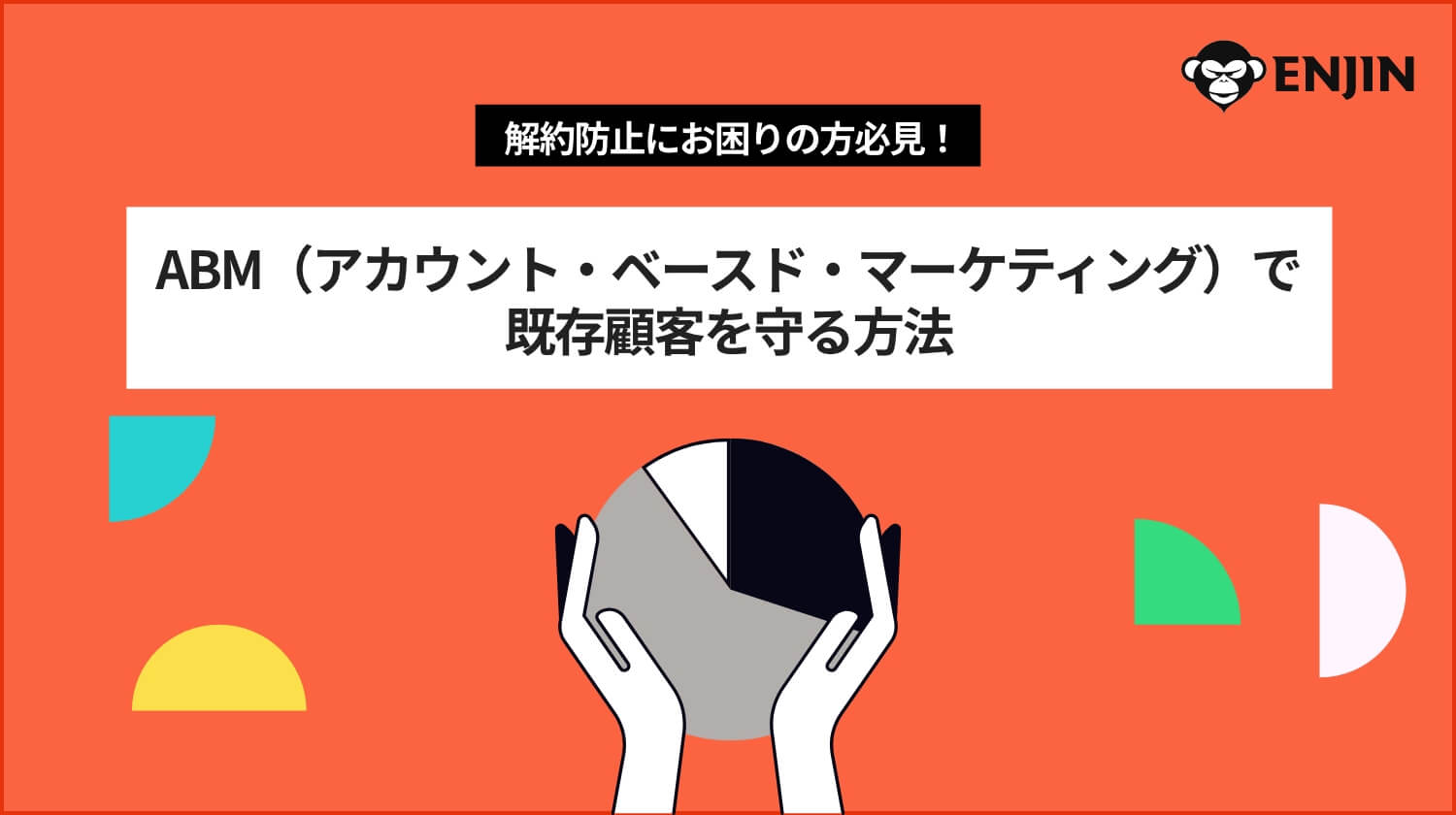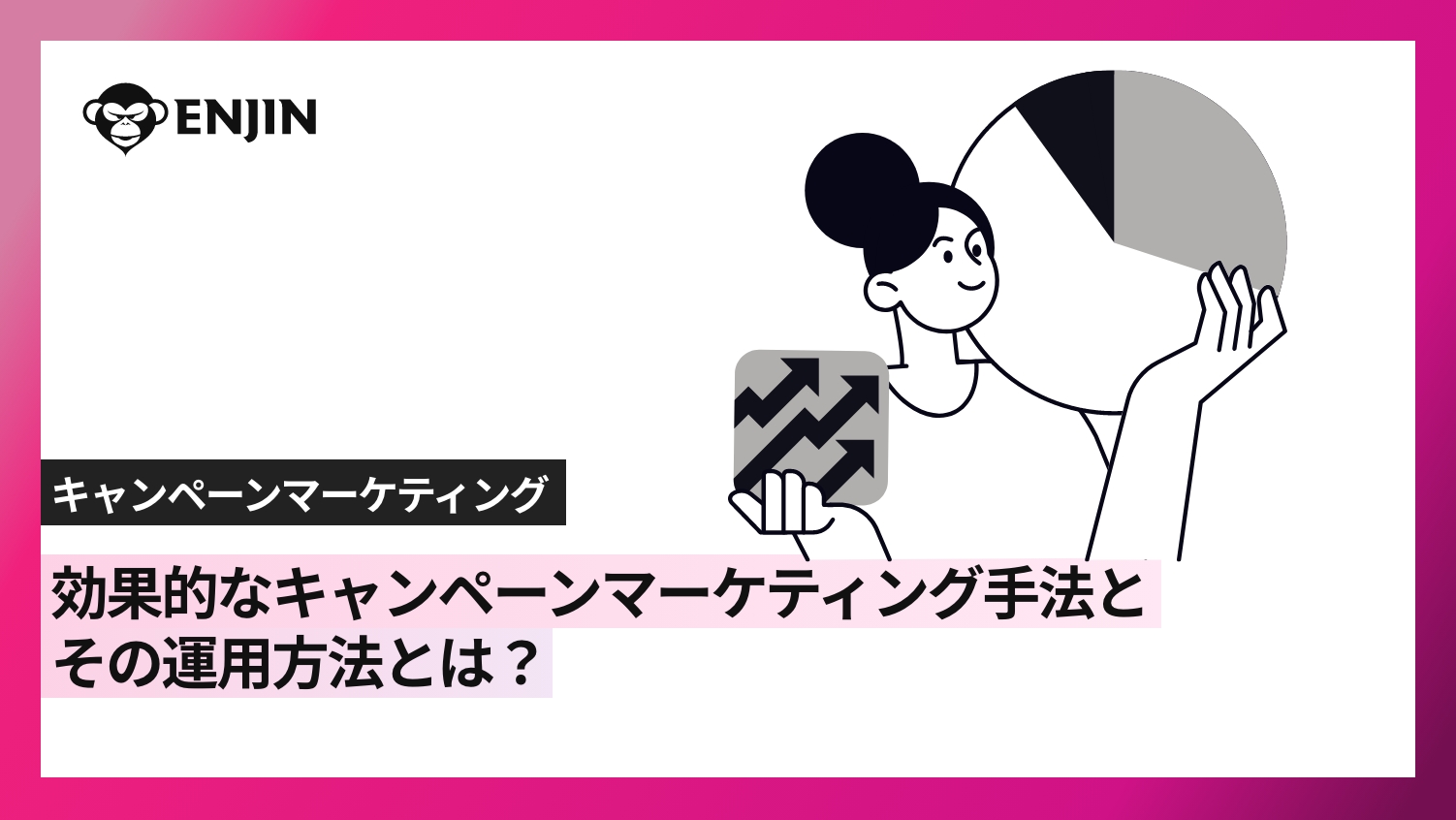BtoB企業向けマーケティング支援サービスの活用法!導入前の準備と連携方法について徹底解説

BtoBマーケティングの現場では、「社内リソースやノウハウ不足で、施策が思うように進まない」「成果がなかなか上がらず、どこを改善すべきか不明瞭」といった課題が慢性的に存在します。顧客行動や市場環境が急速に変化し続ける現代において、これらの課題を自社だけで解決するのは極めて困難です。
外部のマーケティング支援サービスをいかに有効に活用するかは、BtoB企業のマーケティング活動を効果的に推進し、事業成長を加速させるための重要な経営戦略の一つとなっています。
この記事では、BtoB企業が外部のマーケティング支援サービスを最大限に活用するために、導入前に準備しておくべき戦略的なポイントや、支援会社との具体的な連携方法を解説します。
▼目次
BtoB企業のマーケティング担当者が支援サービスを活用する理由
BtoB企業のマーケティング担当者が外部の支援サービスを利用する背景には、単なる業務代行を超えた、より戦略的な意図があります。ここでは、担当者が外部の支援サービスを活用する主な理由について、もう一歩踏み込んで見ていきます。
恒常的な社内リソースの限界と外部活用の必要性
BtoBマーケティングは、戦略の立案から施策の実行、効果測定、改善まで、プロセスが多岐にわたります。必要とされるスキルも、デジタル広告、SEO、コンテンツ制作、MA運用、データ分析など幅広く、「少数精鋭のマーケチーム」でこれらすべてを内製でカバーするのは現実的に負荷が高くなりがちです。
とくに、営業部門との連携が必須となるBtoBビジネスでは、
- マーケと営業の役割分担
- リードの定義や引き渡し基準
- 商談化以降のフォロー体制
といった「協業の設計」も重要なテーマになります。
ここまでを社内だけで設計・運用しきるのは、担当者に過度な負担がかかりやすい領域です。
外部支援サービスを活用することで、
-
不足している専門スキルや工数を補完できる
-
施策実行のスピードや量を維持・向上できる
-
社内メンバーは「判断・合意形成」に集中できる
といったメリットが得られ、結果として全体の業務を効率的に前進させられます。
さらに、社外の専門家が第三者の視点で入り込むことで、社内では見落とされがちな構造的な課題の発見や、これまでにないアプローチの提案が生まれる点も大きな価値です。
高度な専門知識とノウハウの吸収
マーケティング支援会社は、さまざまな業界・規模の企業を支援してきた経験から、成功・失敗のパターンを体系化した独自のノウハウやメソッドを蓄積しています。そのため、クライアント企業はゼロから試行錯誤を重ねるよりも早く、実績にもとづく実践的な知識やスキルを自社のマーケティング活動に取り入れられるのが大きなメリットです。
また、多くの支援会社は、
-
SEOやコンテンツに強いパートナー
-
デジタル広告に特化したパートナー
-
MA/CRMの導入・活用に長けたパートナー
など、特定領域に強みを持つ企業とのネットワークを有しています。これにより、単一の支援会社だけではカバーしきれないテーマにも柔軟に対応でき、企業ごとのニーズに合わせた高度で専門的なサポートを受けることが可能になります。
外部パートナーを「手足」として使うだけでなく、「知見の供給源」として活用することが、BtoB企業のマーケティング力を中長期的に底上げしていくうえで重要な視点と言えるでしょう。
【関連記事】新規施策を成功に導く「伴走支援」とは?マーケティング担当者が感じる“やりきれない”を解消する、実行力の処方箋
BtoB企業が支援サービス活用で期待できる効果
支援サービスの導入によってどのような成果が得られるのかは、多くの企業が気になるポイントです。ここでは、外部支援を活用することで得られる主な効果について整理します。
効率的なリード獲得と新規開拓の推進
また、自社だけではアプローチが難しい新たなターゲット層へのリーチや、既存顧客の潜在的なニーズの掘り起こしもスムーズになります。これは、マーケティング支援会社が持つ幅広いチャネルの活用と豊富な実績があってこそ実現できる成果です。
マーケティング支援会社は、戦略的な施策設計やターゲティングを通じて、Webサイトへのセッション数(訪問数)や問い合わせ数の向上を促進します。
彼らが持つ専門ノウハウ・分析力・チャネル活用力により、質の高いリードを効率的に獲得できる体制が構築できる点は大きなメリットです。
また、自社内ではアプローチが難しいターゲット層へのリーチや、既存顧客の潜在ニーズの掘り起こしもスムーズに行えるようになります。これは、支援会社が多くの実績をもとに持つ知見と、幅広いチャネル活用があるからこそ実現できる成果です。
【関連記事】リードジェネレーションのすべて!施策の成果を高める専門知識を伝授
営業効率の向上と商談化率の改善
マーケティング部門がリード獲得から育成までを担い、営業部門が商談に専念できる体制を構築すると、営業活動の生産性は大きく向上します。とくに、BtoBビジネスは長期的な関係構築が前提となるため、マーケと営業の効率的な役割分担が、継続的な売上向上につながるのが特徴です。
さらに、支援会社のリソースを活用することで、
-
見込み客の関心度を可視化するスコアリング
-
リードごとの最適なアプローチタイミングの把握
-
商談化につながりやすいシナリオ設計
などがスムーズに行えるようになり、商談化率の改善や成約までのリードタイム短縮も期待できます。
こうした仕組み化は、営業現場のストレス軽減やモチベーション向上にも効果的です。
社内へのナレッジ蓄積と自走体制の強化
マーケティング支援会社の価値は、外部に業務を委託できることだけではありません。
支援会社を通じて得られる専門知識や運用ノウハウが社内に蓄積されることで、中長期的なマーケティング体制の強化につながる点も大きな魅力です。
-
トレーニング
-
施策伴走
-
データ分析の共有
-
運用フローの整備支援
といった活動を通じて、担当者のスキルアップが促され、社内にナレッジが蓄積されていきます。
最終的には、「外部がいなくても運用できる」自走型のマーケティング組織を構築できるため、長期的な競争力向上にも寄与します。
外部パートナーから得た知見を積極的に活用し、社内のマーケティング力を底上げしていくことが、企業の持続的成長を支える重要なポイントとなるでしょう。
BtoB企業のマーケティング支援サービス導入に向けた準備
BtoB企業がマーケティング支援サービスを導入する際は、その効果を最大限に引き出すために、導入前の適切な準備が欠かせません。ここでは、事前に押さえておくべき重要なポイントを解説します。
現在の課題と目標の整理
最初のステップは、自社が抱えている現状の課題を正確に把握することです。
「どこで成果が止まっているのか」「改善すべきボトルネックは何か」を明確にし、全社の事業目標と整合するマーケティング目標を設定しましょう。
そのうえで、
-
ターゲット企業
-
顧客像(ペルソナ)
-
自社の提供価値
-
競合の強み・弱み
-
市場トレンド
といった要素を整理することで、戦略設計の精度は大きく高まります。
さらに、施策の評価を客観的に行うために、KPI(重要業績評価指標)を数値で定義することも必須です。
「問い合わせ数」「MQL数」「SQL数」「商談化率」など、自社の目標に適した指標を設定しましょう。
社内体制と担当者の決定
外部支援を最大限に活かすためには、社内の役割分担を明確にしておくことが非常に重要です。
-
どの部門がどの種類のリードを担当するのか
-
マーケ→営業→CSの流れをどうつなぐのか
-
意思決定のフローはどうするのか
といった基準を事前に定義しておくことで、プロジェクトの進行がスムーズになります。
また、施策の管理や支援会社との窓口を担当する専任の担当者(プロジェクトオーナー)を置くことで、意思決定が速くなり、連携の品質が向上します。
部門横断でコミュニケーションが取りやすい体制をつくることが、マーケティング施策の成功に直結します。
予算設定と成果指標の策定
マーケティング支援サービスは、支援内容や提供範囲によって費用が大きく異なります。
そのため、事前に「投資対効果」を踏まえた予算設定が欠かせません。
導入前には複数の支援会社を比較し、
-
サービスの提供範囲
-
支援実績
-
契約形態
-
報酬体系
-
運用体制
などを総合的に確認し、自社に最も適したサービスを選ぶことが重要です。
また、導入後の成果を測定できるよう、
-
KPI(短期/中期)
-
KGI(最終目標)
-
評価のタイミング
-
数値の基準値(ベースライン)
を事前に決めておくことで、納得感のある運用が可能になります。
明確な目標設定と事前準備が、支援サービスを「投資で終わらせず成果につなげる」ための鍵となります。
BtoB企業とマーケティング支援会社の連携方法
BtoB企業がマーケティング支援サービスを導入する際、その効果を最大限に引き出すためには、支援会社との密接な連携が不可欠です。ここでは、成果につながる連携のポイントを具体的に解説します。
定期的な情報共有とすり合わせ
効果的な連携には、定期的かつ正確なコミュニケーションが欠かせません。
クライアント企業の担当者と支援会社の担当者が常に情報を共有し、双方が同じゴールと現状認識を持てている状態が、成功への前提条件となります。
そのために、以下のようなコミュニケーションの仕組みづくりが重要です。
-
定例ミーティングの開催
-
進捗レポートの提出・レビュー
-
課題共有のためのチャネル整備
-
意思決定のフローの明確化
これらを整えることで、プロジェクトの流れをスムーズにし、認識のズレや誤解による施策遅延を防げます。
結果として、状況に応じて柔軟かつ迅速な改善が可能になります。
データ共有と効果測定
マーケティングの成果は感覚ではなく、データに基づいて判断することが重要です。
Webサイトの流入数・問い合わせ数・商談化数などの定量データを支援会社と共有することで、次の施策設計や改善ポイントがより明確になります。
また、営業部門との連携強化においてもデータ共有は不可欠です。
-
リードの属性情報
-
過去の接点履歴
-
スコアリング状況
-
商談化の成否要因
などを共通の基準で扱うことで、リード引き渡し時の情報漏れや認識の齟齬を防ぎ、営業の動きも滑らかになります。
さらに、データに基づいてPDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を継続的に回すことで、施策の精度が高まり、マーケティング全体のパフォーマンスを継続的に向上させることができます。
継続的な改善と最適化
BtoBマーケティングは「一度、リリースすれば終わり」ではなく、戦略→施策→育成→営業連携→既存活用→改善 の複数ステップで構成される長期戦です。
そのため、継続的な改善が成果の質を左右します。
-
成果が出た施策は他チャネルへ展開する
-
反応が弱い施策は理由を分析し改善を加える
-
顧客行動や市場環境の変化に合わせて施策を最適化する
こうした改善の積み重ねに、支援会社の客観的視点や専門ノウハウを掛け合わせることで、より高い成果が生まれます。
支援会社と共に改善活動を継続することで、市場・顧客ニーズの変化にも強くなり、長期的な事業成長につながるマーケティング体制を構築できます。
まとめ
この記事では、BtoB企業がマーケティング支援サービスを導入する際に知っておくべき重要なポイントを解説しました。
- BtoB企業がマーケティング支援サービス活用で期待できる効果
- BtoB企業のマーケティング支援サービス導入に向けた準備
- BtoB企業とマーケティング支援会社の連携方法
マーケティング支援サービスを活用することで、社内リソースやノウハウの不足を補い、質の高いリード獲得や営業効率の向上、さらには社内への知見蓄積といった多くのメリットが期待できます。
サービス導入前には、まず自社の課題と目標を明確にし、社内体制や予算をしっかりと整理することが成功への鍵となります。そして、導入後は支援会社との密な連携を通じて、施策の継続的な改善を図っていくことが非常に重要です。
マーケティング担当者として、外部パートナーの専門的な力を柔軟に取り入れ、それを自社の成長へとつなげていく姿勢が求められます。
『猿人』では、戦略設計から実行、効果測定までワンストップでサポートし、企業ごとの課題に合わせた柔軟な提案をしています。
- 「何から始めていいかわからない」
- 「自社に合ったマーケティング戦略を立てたい」
- 「限られたリソースで最大限の効果を出したい」
といったお悩みをお持ちでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
貴社の施策設計に役立つTodoリストや進行表、RFP(提案依頼書)のひな型といった資料もご用意していますので、ぜひチェックしてご活用ください。