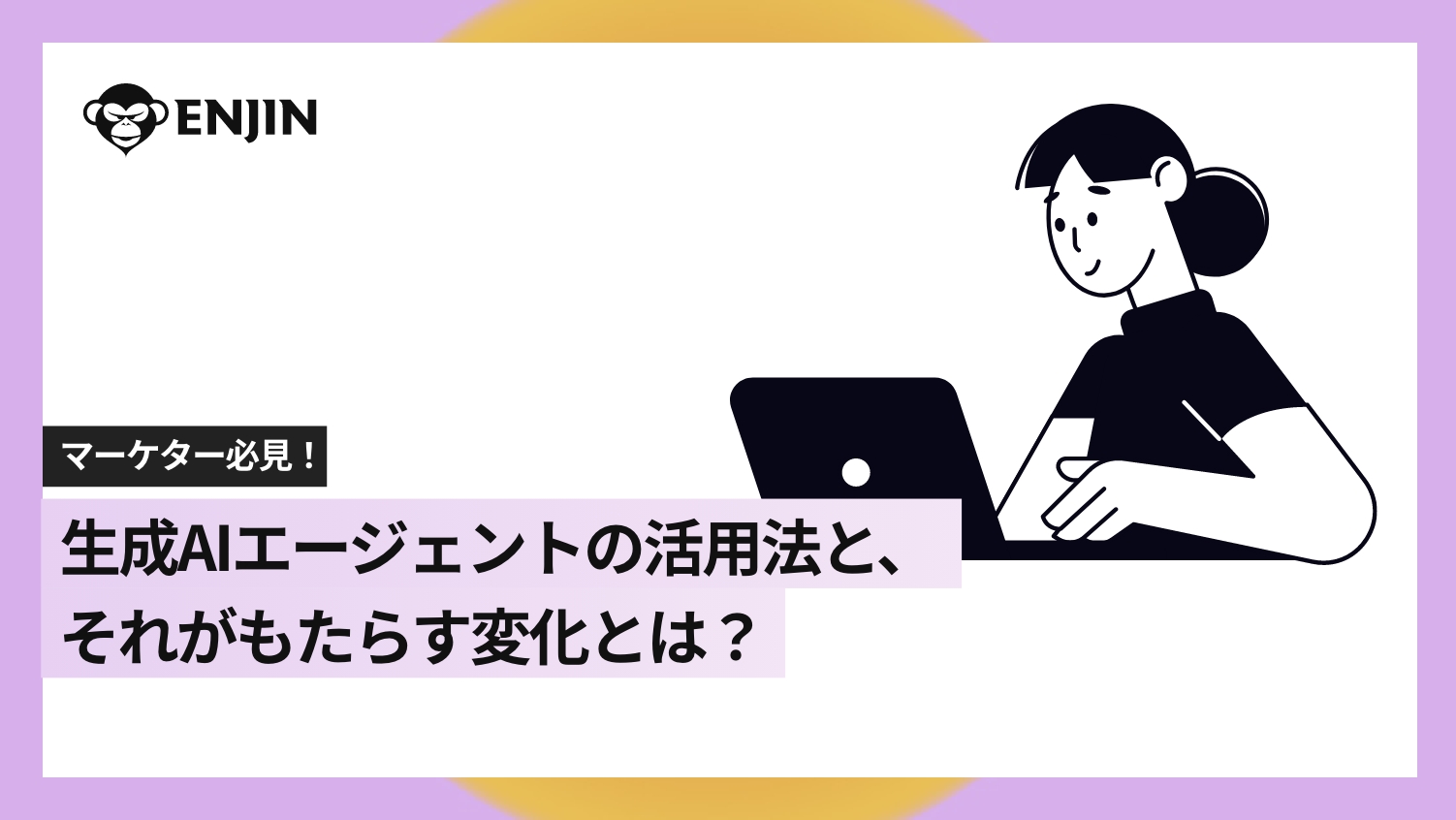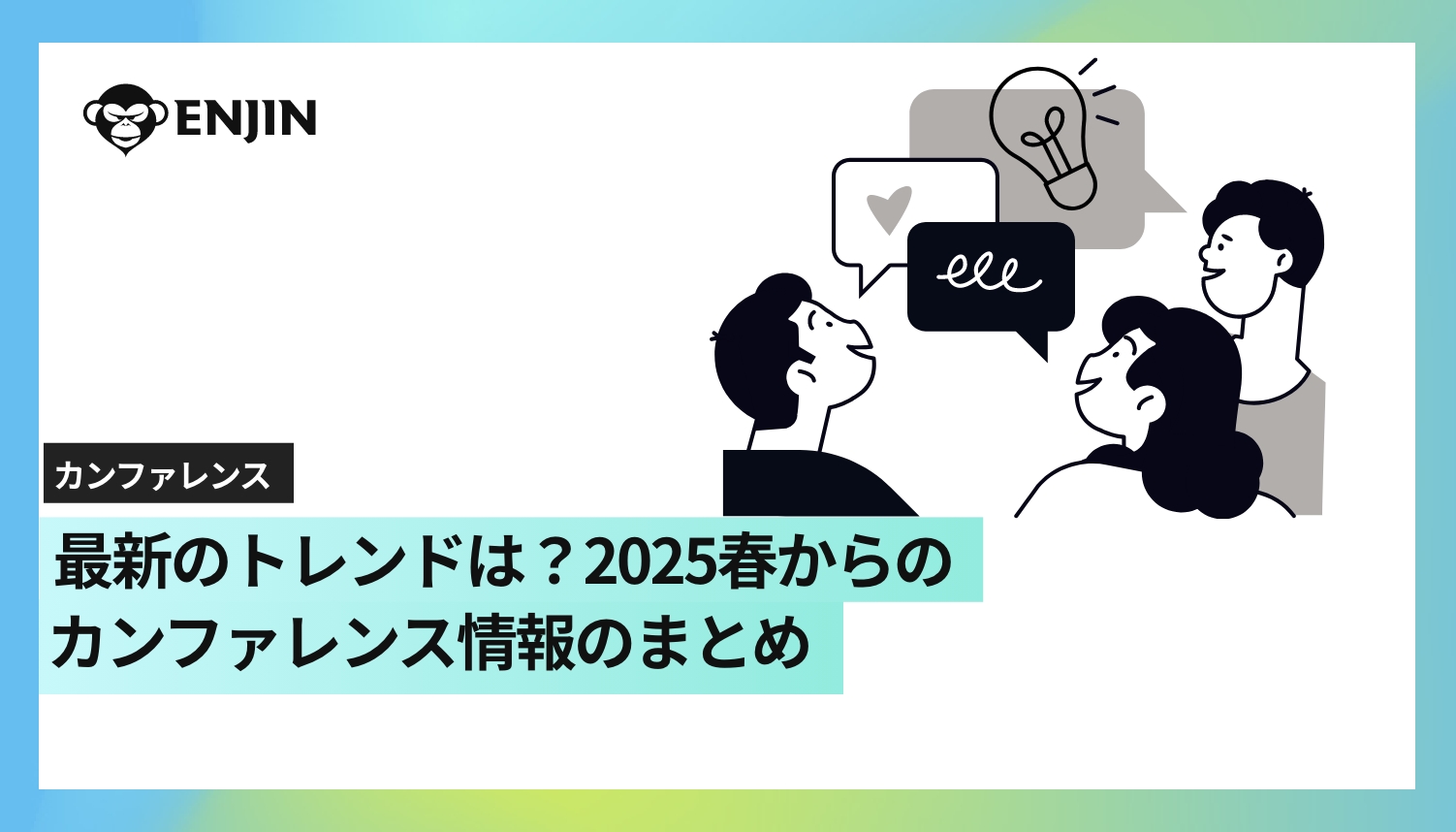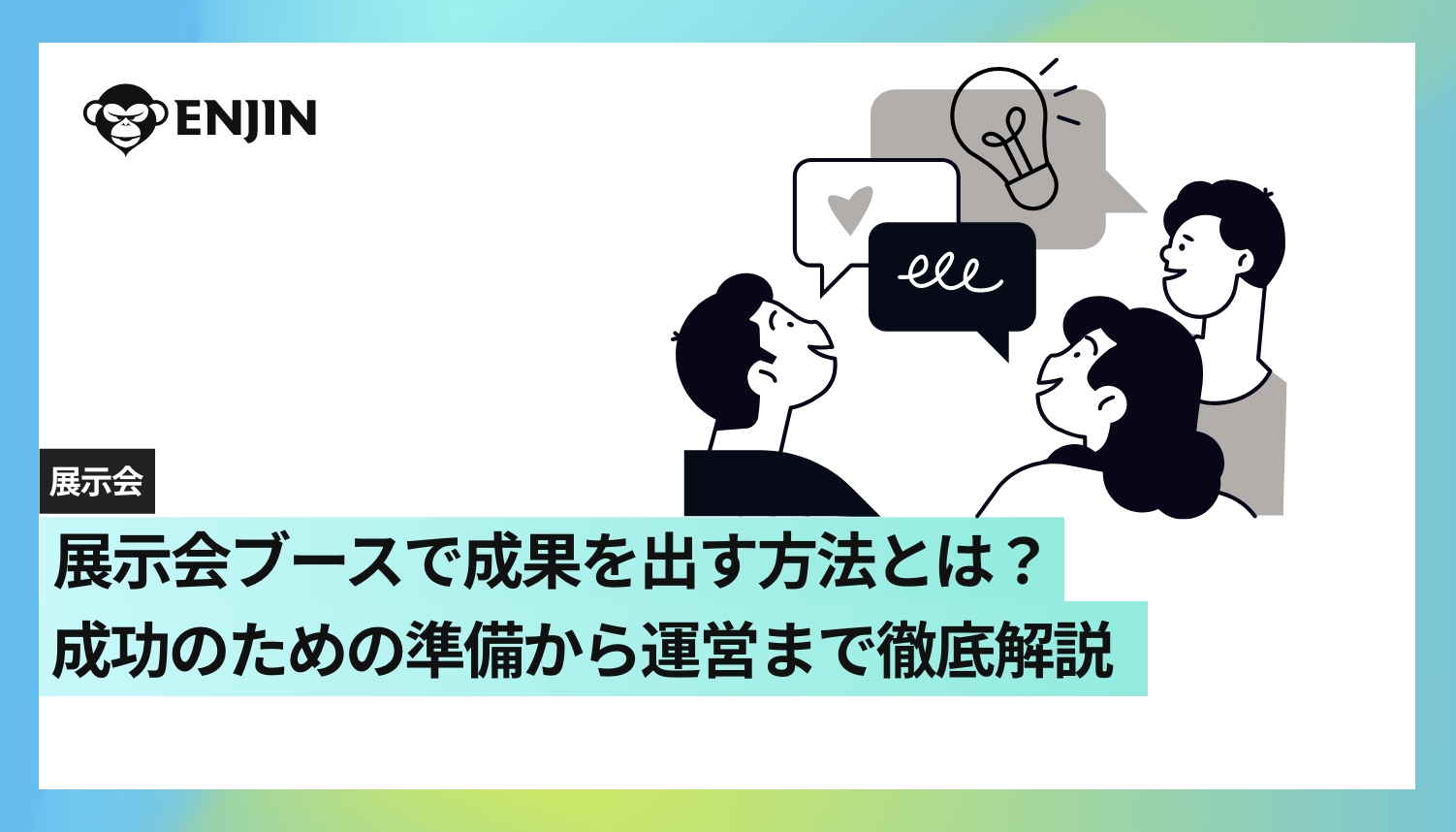新規施策を成功に導く「伴走支援」とは?マーケティング担当者が感じる“やりきれない”を解消する、実行力の処方箋

新しいマーケティング施策を考えるときって、ちょっとワクワクしますよね。
「これ、ウチにとって新しい挑戦になりそう」「ターゲットに刺さる気がする」
──そんな期待を胸に、企画や戦略を練り始める瞬間は、まさにマーケターの腕の見せどころ。
でもその一方で、こんな気持ちにモヤっとしたことはありませんか?
「この企画、面白いと思うんだけど、社内を巻き込める気がしない」
「戦略は作った。でも手が足りなくて、次のアクションになかなか進めない」
「事前調査も分析もしたのに、なぜか施策の効果が出ない」
──そう。アイデアも戦略もあるのに、“やりきれない”まま終わってしまう。
マーケティング施策ではよくある話です。
なぜそんなことが起きるのか。
それは、今のマーケティングが抱える背景に、複雑化した顧客接点、ROIへの厳しい目、社内連携のハードルなど、1人や1部署ではどうにもできない構造的な壁があるからです。
そんなときに、心強い存在になってくれるのが「伴走支援」です。
単なるアドバイスではなく、まるで外部にいる“もう1人のチームメンバー”のように、戦略から実行、改善までを一緒に走り抜けてくれる存在です。
この記事では、マーケティング担当者が新しい施策を確実に前へ進めるために、「伴走支援」がどんな価値を発揮するのか、その中身と活用のヒントをまるっとご紹介します。
▼目次
「伴走支援」って何?
新しいマーケティング施策を立ち上げた際、もちろん戦略を立てるだけでは終わりません。
むしろ本番は、そこから「じゃあ誰が動かす?」「どう進める?」という“実行フェーズ”こそが勝負どころですよね。
でも実際には、こんな壁にぶつかることも多いはず。
「いい戦略が描けたのに、手を動かす段階で止まってしまった」
「ターゲット像もコンテンツも決めたのに、社内の動きが鈍くて前に進まない」
どれも“あるある”ですよね。
そんなとき、思い出してほしいのが「伴走支援」という選択肢です。
いわゆる「コンサルティング」とはちょっと違って、机上のプランだけで終わらず、現場に入り込んで、戦略から実行、改善までを一緒に走り抜けてくれる存在なんです。
伴走支援の特徴とは?
ひとことで言うなら、「提案して終わり」ではなく、「最後まで一緒にやる」スタイルです。
プロジェクトの立ち上げから施策の実行、そして振り返りのPDCAまで──まるで社内チームの一員のように寄り添って並走してくれるのが「伴走支援」の最大の特徴です。
従来のコンサルティングは、課題分析から戦略立案を強力にサポートしてくれますが、実行まではサポートしてもらえないことがあります。しかしそれでは「で、(通常業務に追われるこの状況で)誰がやるの?」という疑問が生まれますよね。
そんな中、伴走支援ならこういった点までカバーできます。
- 実行計画を一緒に作成(戦略をちゃんとタスクに落とし込む)
- 実行フェーズの支援(たとえば、イベント現場の運営や広告のレポート作成など)
- プロジェクトMTGへの定常参加(週次/隔週の定例など)
- タスクの優先順位づけやリソース配分の整理
- KPIの進捗レビューや改善アクションの提案
つまり、「一緒に考え、一緒に動き、ちゃんとやりきる」のが、伴走支援なんです。
【関連記事】伴走支援型のコンサルティングのサービス内容を徹底解説!基本的な役割と選ぶ際のポイント
なぜ今、「伴走支援」が求められているのか?
近年、特にBtoB業界では新しい施策を立ち上げる難易度が一気に上がっています。
- 市場の変化が早く、顧客ニーズが見えにくい
- 社内の実行リソースが足りない(むしろ減ってる)
- MA / CRMなどのツールはあるけど、数が多すぎて使いこなせない
──とくに現場では、こんな声が増えています。
「戦略は立ててもらったけど、実行部分での社内のリソースが逼迫してしまい、結局プロジェクトが停滞」
「計画はしたけど、“誰が”、“いつまでに”、“どう動くか”まで落とし込めず、なんとなく立ち消えてしまった」
ここからわかるのは、どんなに優れた戦略でも、それを動かす体制がなければ“絵に描いた餅”になってしまうということ。
そこで活躍するのが、伴走支援です。
戦略策定だけでなく、実行フェーズまでしっかり入り込み、一緒に手を動かして施策を前に進めていく。
しかも、ただ実行部分のみをサポートするのではなく、現場の“自走力”を高める支援スタイルで社内の若手メンバーの育成にもつながります。
「成果を出す」だけじゃなく、「チームが考え、動き、成長する」までを支援する。
それが、いま求められている“新しい支援のかたち”、伴走支援なんです。
マーケティング部門が抱える“新規施策あるある”
企画や戦略の立案までは順調でも、実行フェーズで動きが止まる──
なんてシーン、BtoBのマーケティングの現場では、珍しくありません。
「やってみたい気持ちはある。でも今はどう考えても手が回らない…」
「企画までは良かったのに、いざ進めようとすると動けない…」
こうした“あるある”に悩まされている方、多いのではないでしょうか。
新しいことに挑戦する場面では、マーケティング部門は最前線に立つことが少なくありません。
そのぶん、リソースも判断軸も情報も足りない中での“手探りな進行”になりがちです。
ここでは、そんな現場でよくある「詰まりポイント」をいくつかご紹介します。
顧客ニーズがつかめない問題
新規施策の最大の難所、それは「誰に、何を、どう届けるか」が曖昧になりがちなこと。
営業部門との連携が不足していたり、一次情報が拾えていなかったりすると、表面的なニーズや仮説に頼った施策になってしまい、結果的に…
「よさそうなコンテンツは出てるけど、全然反応がないね」
みたいなフィードバックが来てしまう、なんてことに。
とくにBtoBの場合、顧客の検討プロセスはかなり複雑です。
目に見えるニーズではなく、“その奥にある課題”や“解決したい背景”まで深掘りできないと、施策が刺さりません。
差別化が難しい・ブランドの軸がブレる...
「うちの強みって何だっけ?」
競合の多い市場では、自社の個性や価値が埋もれてしまいがちです。
ブランドコンセプトが定まらないまま施策を進めると、広告やコンテンツの方向性もブレてしまい、ユーザーに一貫性のある印象を届けるのが困難になります。
他社事例を参考にするのはもちろん大事ですが、“自社ならでは”の切り口や軸がなければ、結局埋もれてしまいます。
独自の価値、独自の言葉、独自の伝え方、これを言語化し、施策に落とし込むのがマーケティングのお仕事です。
【関連記事】BtoBマーケティングとは?効果的な戦略立案の方法と主要施策を紹介
「全部ひとりでやるのは、無理。」──だから“プロと走る”という選択肢を
新しい施策に挑戦しようとするとき、「これ、本当に全部ひとり(or うちのチーム)で回せるんだっけ…?」
そんな不安がふとよぎったこと、ありませんか?
企画、制作、集客、調整、実行、レポート……想像以上に手間も工数もかかるのが、新規施策というもの。
そんなとき頼りになるのが、現場に入り込んで一緒に走ってくれる「伴走支援のプロ」です。
ここでは、伴走支援を導入することで得られる、代表的な3つのメリットをご紹介します。
1. 多角的なプロの知見が、いまのチームに加わる
マーケティング施策は、マーケだけで完結しません。
営業、開発、CS、制作、分析……とにかく、いろんな視点とスキルの連携が必要です。
でも、社内リソースだけですべてをまかなうのは難しいですよね。
伴走支援では、戦略立案から制作・実行・改善まで、一気通貫でサポートできる“プロのチーム”が、必要なタイミングで必要な役割を担ってくれます。まるで「いま足りてない部分をピンポイントで補強してくれる、臨時のメンバー」が加わる感覚です。
2. “やってもらう”から、“自分たちでできる”チームへ
伴走支援の本質は、アウトソースではありません。
施策を一緒に動かしていく中で、「意思決定の軸」や「注力すべきポイント」が自然と現場に定着していきます。
結果として、プロジェクト終了後も「自分たちで仮説を立てて、次の一手を打てる」そんな“自走できるチーム”に育っていきます。単発の支援で終わらず、“再現性のある成功パターンをチーム内に残せる”のが、伴走支援の強みです。
3. 仮説検証のスピードが加速する
新規施策では「早く試し、早く学ぶ」ことが成果のカギを握ります。
しかし、社内だけで試行錯誤を繰り返すのは、時間的にも精神的にも大きな負担です。
そこで、伴走支援のプロが入ることで、仮説検証のフレームワークが整い、PDCAサイクルを回すスピードがグッと上がります。市場の反応を見ながら即座に訴求軸をチューニングしたり、Lを週次改善したりと、スピーディーかつ柔軟な意思決定が可能になります。
「正解が見えない状況でも迷わず動ける」
――これって、意外と大きな差を生むと思いませんか?
Q.「で、猿人さん。結局どこまでやってくれるの?」──A.「けっこうやります」
ここまで読んでみて、「伴走支援って、何だか便利そうだけど、猿人さん。実際のところ、どこまでやってくれるの?」
そんな疑問、当然ありますよね。結論から言うと「正直。めっちゃ、やってくれます」。
たぶん、みなさんの想像よりずっと、“深く入り込む”スタイルです。
いわゆる「相談に乗ってくれる人」ではなく、実務を一緒にやりきるパートナー的な存在になります。
ここでは、私たちが実際に提供している伴走支援の内容を、「戦略 → 実行 → 評価 → 組織定着」の4ステップで紹介します。
Step 1|戦略設計:フワッとした構想を“勝てる設計図”へ
新しい施策の立ち上げ時、「いいアイデアはあるけど、どこから手をつけていいかわからない…」という状態になるとき、ありませんか?
とくにマーケティング部門では、構想と実務の間に大きなギャップがあることも。
伴走支援では、その“ふんわり”を具体化して、実行可能な戦略に落とし込むところから始まります。
たとえば整理するのはこんな要素
- KGI・KPIの定義と成功条件の見える化
- ペルソナやセグメントの設計
- 訴求軸・メッセージとタッチポイントの整理
- ステークホルダーの巻き込み方(社内外)
たとえば展示会施策であれば、来場者の導線設計や意思決定ポイントの整理も含め、後の実行段階で迷わない“共通言語としての戦略”を一緒に整えていきます。
Step 2|施策実行:泥臭く、一緒に手を動かします
「戦略だけ渡されても、実行するリソースもないんですけど…!!!」
――ご安心ください、私たち、けっこう泥くさく動きます。
展示会なら小間位置選定会から施工の立ち合い、会期初日の立ち上げから撤収まで、現場に実際に入って手を動かすのが私たちの伴走スタイルです。
たとえば、オフライン施策ならこんな支援を行います。
- 展示会やセミナーの企画・運営・動線設計
- 集客施策のプランやメディアバイ、レポーティング
- ノベルティ/営業資料/運営マニュアルの作成
- 営業連携やフォローアップ体制の整備
「展示会に出ることは決まっているけど、何をどの順番で準備すべきか分からない」といったお悩みをお持ちの場合、来場者導線の設計・装飾コンセプトの立案・ノベルティや資料の準備・リード取得後の営業連携フローの策定など、実務レベルでの実行支援を提供します。
もちろん、オンライン広告での告知やSNS配信、オウンドメディアやメディアでの事後レポート掲載なども対応可能です。
「オフライン×オンライン」を横断した顧客体験の設計もサポートします。
Step 3|KPI設計とPDCA:やりっぱなしにしない仕組みづくり
施策を実施しても、振り返りと改善がなければ“やりっぱなし”になってしまいます。
伴走支援では、戦略と連動したKPIを定義し、実行後も効果検証と改善提案までしっかりサポートします。
たとえばイベント施策の場合、
- 来場者数やブース訪問率
- リード獲得数(名刺/アンケートなど)
- 商談化率
- メール開封率・資料DL率
といった指標に基づき、振り返りレポートや改善案を提案します。
こういった成果を“見える化”することで、次回施策への学びを蓄積していきます。
Step 4|ノウハウ定着:属人化させず、再現可能に
どんなに施策がうまくいっても、担当者の頭の中だけに知見が残っていては意味がありません。
伴走支援では、実施した施策のノウハウを形式知として社内に定着させる支援も行います。
たとえばこんな情報の整理と共有をします。
- 来場者対応やブース運営のベストプラクティス
- 想定問答集・トークスクリプト
- 成功事例と改善点のレポート
- マニュアルやチェックリストのテンプレート化
「誰がやっても、一定の成果が出せる」
そんな状態を目指して、“再現できる仕組み”をチームに残します。
戦略だけで終わらせない。「やりきり力」を支える伴走支援という選択
新規施策の成功には、優れたアイデアや戦略だけでなく、「誰が、どうやって、どこまでやりきるか」が問われます。
とはいえ、マーケティング部門だけで全てを抱え込むのは現実的ではありません。
リサーチや企画立案、社内調整、クリエイティブ監修、イベント運営、営業連携
――これらは一つひとつが丁寧に取り組む必要があり、時間も手間もかかります。
だから今、「プロとともにやりきる」ための伴走支援が求められています。
- 「企画の種はある。でも“カタチ”にできない」
- 「実行フェーズに手が回らず、立ち消えになってしまう」
- 「やりっぱなしで終わってしまい、次につながらない」
そんな“あと一歩”を一緒に走りきる存在として、私たち『猿人』は戦略設計から実行支援、改善・内製化までを一貫してサポートしています。
施策のToDoリストの整理からでも構いません。
展示会の導線設計やセミナー台本の作成、KPIやレポートテンプレートの整備など、私たちは現場目線での支援を得意としています。
「せっかく企画した施策を最後までやりきる力(リソース)がほしい」と感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。